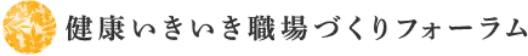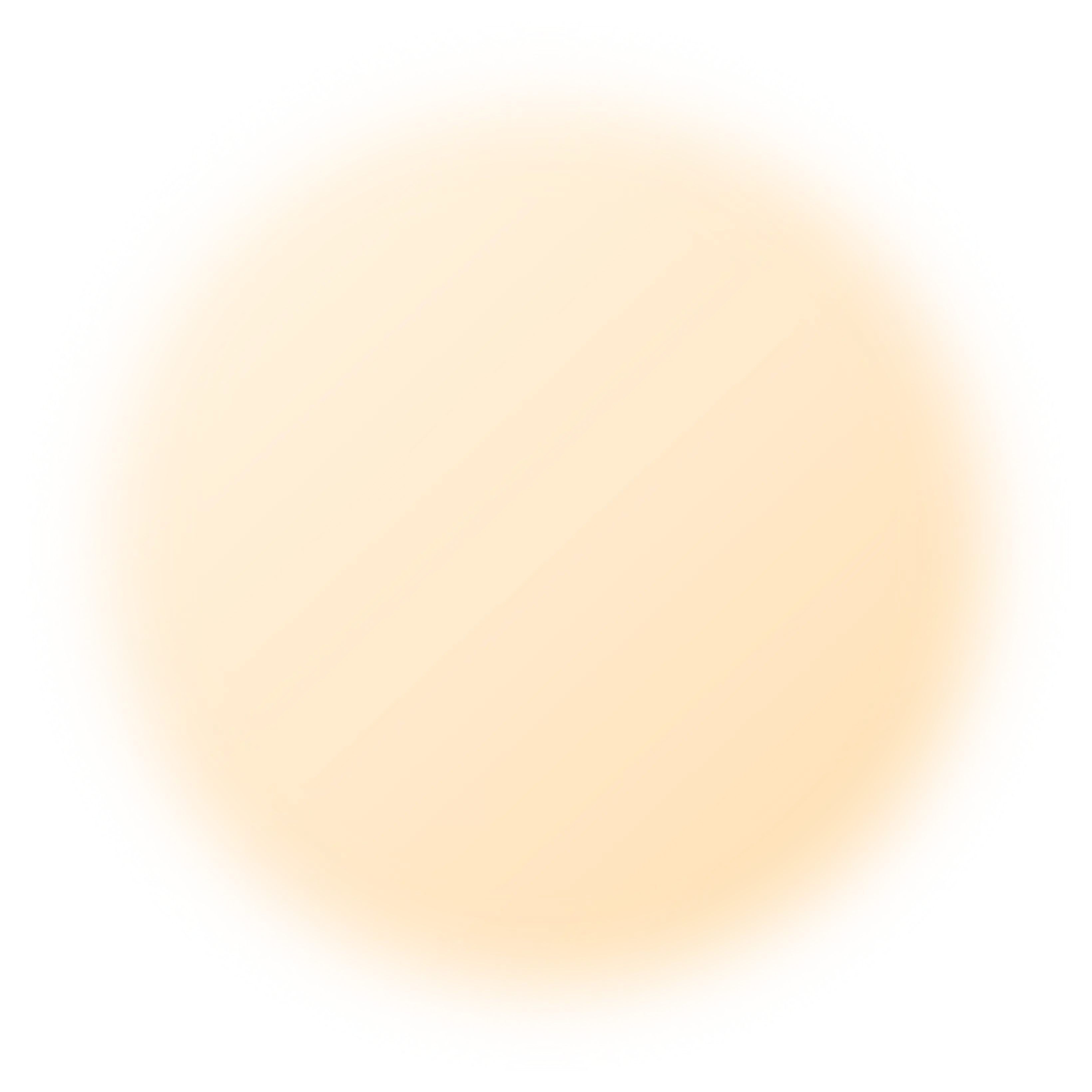2019年7月4日(木)、東京大学医学部2号館 3階大講堂にて夏季シンポジウムを開催しました。
今回のテーマは『労働生産性の向上に寄与する健康増進手法』と題し、学識者から企業幹部まで幅広い分野から論客を招聘し、講演や全体質疑を通じて多彩な意見・問題提起がなされました。
梅雨で降雨のなかでしたが、当日は約100名の方々に参加いただき、盛会となりました。
本シンポジウムのテーマは『労働生産性の向上に寄与する健康増進手法』でしたが、わが国における人口減少と高齢化の進行を背景とし、労働生産性の向上が成長戦略として注目されています。また、経営基盤である人財について、生涯現役社会の実現や健康寿命の延伸が求められるなか、健康増進への関心が高まっています。
今、企業には人財戦略を見直し、ひとりひとりの生産性を長期的視点に立って高めていくことが求められています。その取り組みのひとつとして、働く人が健康でいきいき働ける組織、職場づくりを実践すること、つまり、労働生産性の向上に寄与する健康増進への取り組みが拡がっています。
本シンポジウムは、労働生産性の向上に寄与する健康増進手法について、実証的な研究成果や先進的な企業の取組みについて多様な視点から議論頂き、ご参加企業のより良い経営の実践をご支援するために開催いたしました。
冒頭、フォーラム代表挨拶として東京大学大学院教授 川上憲人様より、健康いきいき職場づくりフォーラム設立からの7年間の経緯や活動についてお話いただきました。また、今回のシンポジウムの主な内容は慶応義塾大学教授 島津明人様が主任研究者を務められた厚生労働省科学研究費による労働安全衛生総合研究事業の成果であることが紹介されました。
■東京大学大学院 川上憲人教授
続いて慶応義塾大学教授 島津明人様より基調講演として『労働生産性の向上に寄与する健康増進手法』と題してお話をいただきました。
まず、平成28~30年度に実施された厚生労働省科学研究費による労働安全衛生総合研究事業プロジェクトの背景と全体概要を説明いただきました。研究課題が労働生産性の向上や職場の活性化に資する効果的な健康管理および健康増進手法の開発であること、また労働生産性の向上と健康増進の両立に関する科学的根拠の蓄積が必要であること、更に研究の全体像に関する概念図と分担研究者が紹介されました。
その後、各論として「労働生産性の関連指標に関する検討」、「ガイドラインの開発」、「マニュアルの開発」いついてお話をいただきました。特に、「ガイドラインの開発」については、業種・職種(卸売業・小売業、看護職・システムエンジニア)の特徴と健康増進プログラム実施時の留意点、具体的な実施事例が詳細に紹介されました。「マニュアルの開発」については、参加型ワークショップ以外にCREW(Civility, Respect,& Engagement in the Workplace)プログラムやジョブ・クラフティングのマニュアルも紹介されました。
最後に、同プロジェクトの成果は島津教授の研究室WEBサイトよりダウンロード可能であることが案内されました。
■慶應義塾大学 島津明人教授
続いて、早稲田大学教授 黒田祥子様より『労働生産性の多面的な指標の検討~経済学指標の検討』と題してお話をいただきました。黒田様は労働経済学がご専門で、働く人のメンタルヘルスや働き方と生産性の関係について、多くの研究成果を発表されています。
ご講演では、最初に「長時間労働是正の最近の動向と生産性向上につながる働き方」についてお話をいただきました。生産性の分母である長時間労働の是正による心身へのプラスの効果は、併せて労働強度の増加ややる気の阻害等のマイナスの影響にも留意する必要があることが説明されました。また働き方が大きく変化していくなかで付加価値といった分子をいかに増加させていくかが重要であることも説明されました。
更に、職場のポジティブなメンタルヘルスは生産性向上につながるかというテーマについて、今回のプロジェクトでの大手小売業でのデータ分析結果について紹介いただきました。その結果として、同一企業内に勤める従業員の間でも雇用形態などによってワーク・エンゲイジメントの度合いに大きな開きがあること、周りのワーク・エンゲイジメントが高いと本人も高い傾向になること、職場のワーク・エンゲイジメントの平均値が高いと売上高もアップする傾向にあること、ワーク・エンゲイジメントの平均値が同じ場合には職場内のワーク・エンゲイジメントのばらつきが大きいと生産性が低くなることをお話いただきました。
■早稲田大学 黒田祥子教授
次に企業事例として、花王株式会社 健康開発推進部長 知久功様より『花王グループの実践~データヘルスを活用したGENKI-Actionの展開』と題してお話をいただきました。知久様は同社において人事、人財開発、勤労、厚生関連分野で豊富な経験をお持ちで、現在は健康保険組合の理事長も兼務しておられます。
ご講演では、同社の20年来の健康づくりへの取り組み(臨床から産業保健へのシフト)、データヘルスに基づくスパイラルアップ(継続的な改善活動)と社外評価の獲得、健康経営推進体制の構築、同社の産業保健の特徴(職域の広さ・多様さ)および社員と家族の健康維持プロジェクトGENKI Projectについてお話をいただきました。
特にデータヘルスの取り組みについては、活動量データである歩数や健診データである内臓脂肪の値とストレスチェック結果や問診で把握しているプレゼンティーイズムなどの関係性を分析し、活動や身体の状態とパフォーマンスの関係を明らかにすることに取り組んでいるとのご話をいただきました。また花王グループの産業保健推進体制として、人事の重点機能として健康開発推進部を独立させ、この部門を核にして各事業場や販売拠点、関係会社に設けている健康相談室を横軸で連携させつつ、健康保険組合と縦軸で密接にコラボヘルスに取り組む仕組みを構築し、健康経営に取り組まれていることを紹介いただきました。
■花王株式会社 知久様
続いて、『労働生産性の向上に寄与する健康増進手法の開発』として、厚生労働省科学研究費による労働安全衛生総合研究事業プロジェクトの3つのテーマについて、分担研究者や実証研究に取り組まれた皆様よりご講演いただきました。
1つ目は『職場環境へのポジティブアプローチ』と題して、一般財団法人京都工場保健会 御池メンタルサポートセンター 専任カウンセラー 内田陽之様よりお話をいただきました。事業場での取組み事例として京都府の日東精工株式会社での新職業性ストレス簡易調査票の結果を活用する参加型ワークショップでの活動内容と結果を紹介いただきました。職場環境は様々な要因に左右されるため定量的な効果把握は難しいものの、実務的な効果が確認できたこと、業務内容や職場風土も勘案した上で本アプローチを導入することが必要であること、ファシリテーターへの初期サポートも検討すべきであることが報告されました。
■京都工場保健会 内田陽之様
2つ目は『思いやり行動向上プログラム』と題して、就実大学 講師 堀田裕司様よりお話をいただきました。職場における思いやり行動とは何か、思いやり行動の意義、思いやり行動向上プログラムの実施概要、同プログラムの実践から得られる効果についてお話をいただきました。同プログラムの目的は職場内での思いやり行動を増やしていくことにあり、人間関係の改善、組織全体の風通しの向上、離職率の低下や生産性の向上といった効果が狙えるとのご紹介がありました。実施事例として病院の看護師23名が参加されたプログラムでは、上司や同僚に対する思いやり行動が増加したとのことです。また一般企業で56名が参加されたプログラムでは職場の一体感も向上したとのことでした。
■就実大学 堀田裕司講師
3つ目は『腰痛・肩こりとメンタルヘルス対策~プレゼンティーイズムを減らしワーク・エンゲイジメントを高めるために~』と題して、東京大学医学部付属病院 特任教授 松平 浩様よりお話をいただきました。労働損失に最も影響している身体の症状は「腰痛・首の痛み」であり、プレゼンティーイズムや労働生産性に大きな負の影響を与えていること、また慢性腰痛のプレゼンティーイズムは抑うつの程度、心身の健康関連QOLと関連があることが紹介されました。また、動作や姿勢による椎間板圧縮力による腰痛借金と呼ばれる状態はぎっくり腰や椎間板ヘルニアの2大事故につながるため、松平様が考案された独自の体操など、腰痛対策の動画説明とデモンストレーションが行われました。
■東京大学医学部付属病院 松平浩特任教授による体操実演の様子
最後に、島津教授の進行のもと、全登壇者の皆様に対して全体質疑が行われました。花王の知久様に対してデータヘルスの分析の詳細に関する質問や、黒田教授に対して経済的な生産性指標やワーク・エンゲイジメントに関する指標に関する質問などが会場から寄せられ、活発な議論が行われました。
■パネルディスカッションの様子。島津先生に進行いただきました
その後、健康いきいき職場づくりフォーラム事務局より今後の活動紹介をおこない、盛況のうちにシンポジウムは閉会いたしました。
【健康いきいき職場づくりフォーラム事務局より】
健康いきいき職場づくりフォーラム夏季シンポジウム2019へ、大変多くの方々にご参加いただき、誠にありがとうございました。
健康いきいき職場づくりフォーラムでは、昨今の働き方改革・健康経営などの動きも踏まえ、職場を働きやすくまた働きがいのある場所に、また個人も健康でいきいきと仕事にやりがいを持てるように、組織・個人の両輪から健康いきいき職場づくりを会員制サービスとして推進して参ります。
9月からはActive Work Place研究会を開催しますので是非ご参加ください。
今後もより多くの皆様に、この活動にご興味をお持ちいただき、会員として一緒に取り組んでいただけますよう、この場をお借りしてお願い申し上げます。