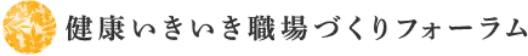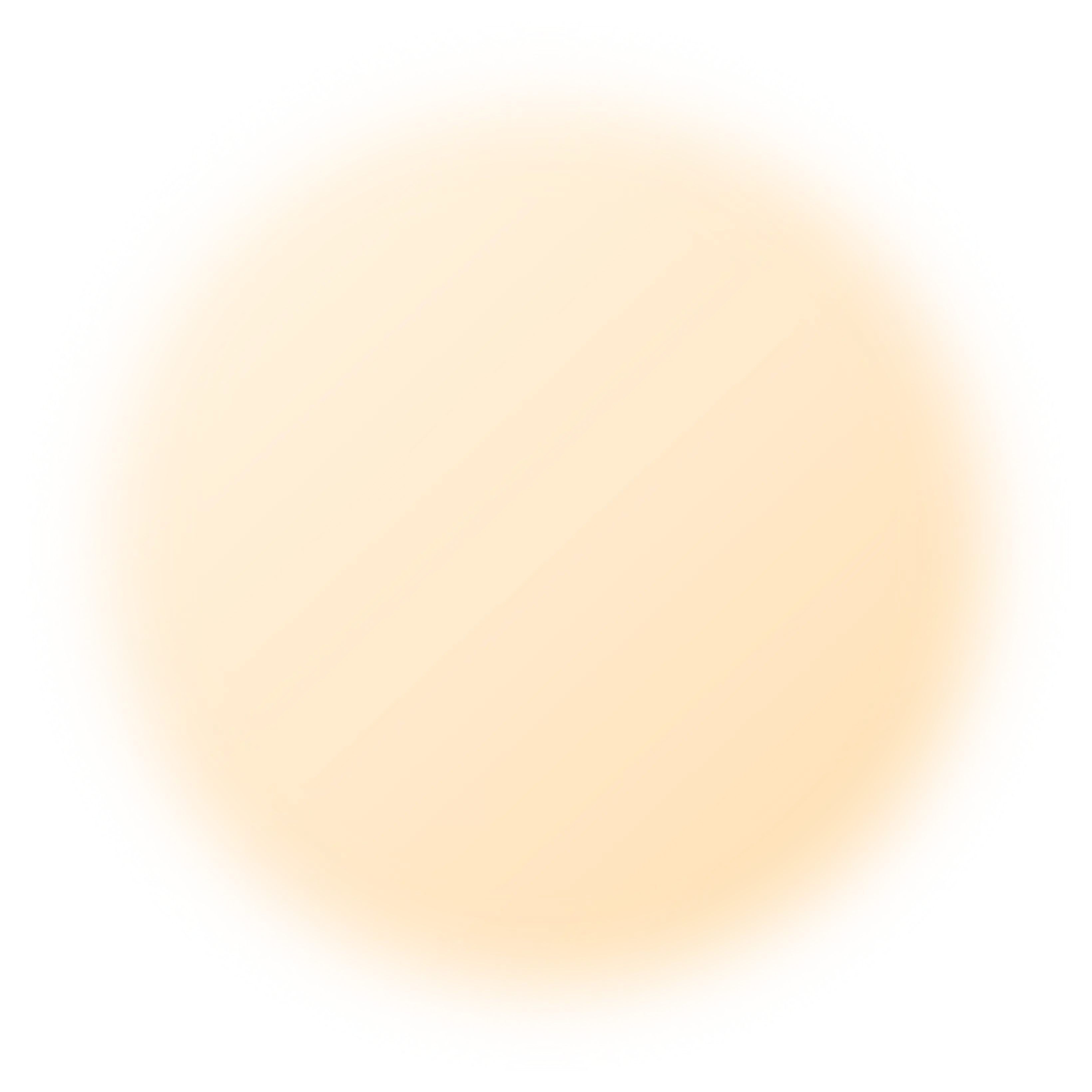去る5月29日、健康いきいき職場づくりフォーラム主催の「経営者シンポジウム」が都内で開催されました。テーマを「社員の心身の健康増進を経営戦略の中にどのように位置づけるか?」とした本シンポジウムには、定員の100名を上回る方々のご来場をいただきました。当日ご来場の皆様、大変ありがとうございました。
冒頭、フォーラムの代表研究者である、東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野 教授の川上憲人氏より、基調講演として「健康いきいき職場づくりとは何か?」と題してお話しをいただきました。続く経営者講演では、伊藤忠商事株式会社の代表取締役 専務執行役員 CAO 小林文彦氏より、「働き方改革への挑戦」と題し、同社が進める働き方改革の経緯と具体的内容、取り組みを成功させる秘訣について、貴重な情報提供をいただきました。
後半のパネルディスカッションは、学習院大学経済学部経営学科 教授の守島基博氏の進行の下、「社員の心身の健康を経営戦略へ」をテーマに行われました。パネリストには、大日本印刷株式会社 専務取締役 神田徳次氏、東京急行電鉄株式会社 執行役員 村井淳氏を迎え、先進企業として進める改革のさらに具体的な内容についてお話しいただきました。
冒頭、フォーラムの代表研究者である、東京大学の川上教授より、基調講演として、「健康いきいき職場づくり」とは何か?についてお話をいただきました。川上教授は、健康いきいき職場づくりは経営戦略として考えるべきであるとの話を前提に、この活動の3つの目標は「ポジティブメンタルヘルスへの着目」、「職場の社会的心理的資源を充実させること」、そして「メンタルヘルスを経営として取り組むこと」であると述べました。また、働き方改革や健康経営との関連についても言及がありました。働き方改革については、政府が示す実行計画の9つの課題の中で、「長時間労働対策」の対応策の一つとして「健康で働きやすい職場環境の整備」が挙げられていることを例えに、健康いきいき職場づくりはその答えの一つになるとお話しになりました。また、健康経営が健康づくりなどの取り組みを通じて健康指標を改善し経営的アウトカムを改善することだとすれば、健康いきいき職場づくりもその活動に一つになるとも言及されました。一方で、健康いきいき職場づくりはマイナスをゼロに戻す活動ではなく、ゼロからプラス、プラスからプラスにしていく活動であることも付け加えました。こうしたポジティブメンタルヘルスの考え方は、厚生労働省でも今後重視すべき課題の一つとして挙がっているそうです。
続く経営者講演として、伊藤忠商事株式会社 代表取締役 専務執行役員 CAOの小林文彦氏より、「働き方改革への挑戦」と題してお話をいただきました。
伊藤忠商事様は、世に先駆けて「朝型勤務」という制度を導入し、社員の長時間労働の削減に成功しておられます。その秘訣について、「働き方改革とは何か」、「どのようにして進めるか」、「当社の進め方」、「どのように進めれば成功するか」、「今後について」という流れでお話をいただきました。講演の冒頭、小林氏からは、「働き方改革」という言葉が先行しているが、それについてきちんと説明できる人は日本にいないのではないか、という問題提起がありました。同社では、政府が掲げる9つの課題についてどれも重要視している中、具体的に施策展開を図ろうとしたとき、長時間労働対策をまずやらなければ、他の施策が展開できなかったため、それを中心課題とされたそうです。
具体的に、同社の改革には2つのフェーズがあるそうです。第一フェーズは2003年~、時の政府の要請もあり「働きやすい会社」への改革に着手されました。しかし、それは「世の中の流れに流されて実施した結果、失敗に終わった」そうです。人材の多様化推進のため、数値目標を設定し、各種制度を拡充したところ、現場とのミスマッチを起こし、メンタル不調者増、戦力外社員増、そして退職者も増加してしまいました。また、本当に頑張らないといけない社員のためであったはずの制度が、制度を多用する社員だけが得をする仕組みになっていたそうです。
そこで、第二フェーズに掲げた目標が「厳しくとも働きがいのある職場」でした。2010年からスタートしたこの変革では、2013年の朝型勤務制度、2016年の伊藤忠健康憲章の制定などを行いました。その改革のデザインは、「魅力ある社内風土」を築くことを基盤にして、生産性向上という課題を、健康経営や社員のモチベーション向上という手段で解決していくものです。魅力ある社内風土を実現するため、同社ではCSRのマテリアリティに、環境や持続可能資源、人権といった項目と同列に労働環境を組み込み、本気で取り組んでおられます。
そして今後は、利益競争だけでなく、周囲が憧れるような会社になることで企業価値を高めて行くことを目標にされています。そのため、働き方改革や健康経営といったテーマが人事労務施策として単体で動くのではなく、CSRやESG(環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance))の方針と融合してやっていくことが大切だと言及されました。「定性でなければ語れない価値観」、「Storyでなければ語れない価値観」を作って行きたいというお話は、健康いきいき職場づくりを推進する際にも心に留めておきたいことです。
■伊藤忠商事 代表取締役 専務執行役員 小林文彦氏
最後に小林氏から、こうしたDNAを塗り替えるような改革を進める際に、多くの企業が引っ掛かる3つのワナについてお話がありました。それらはすなわち、
①社長が担当役員に命ずるだけで終わってしまう改革(社長自身に本気度が足りない)
②社員にやさしいだけの改革(それだけでなく頑張れること支援する)
③改革と業績との関係(一定の業績が読めるようになった時に実行すること。そうでないと、業績低迷の理由を改革のせいにされてしまう)
の3点です。
小林氏のお話は、ご自身が経験された改革の変遷を踏まえた大変具体的で説得力があるものでした。
後半は、「心身の健康増進を経営戦略に」と題したパネルディスカッションを行いました。パネリストに、大日本印刷株式会社 専務取締役 神田徳次氏、東京急行電鉄株式会社 執行役員 村井淳氏をお迎えし、コーディネーターを学習院大学 経済学部経営学科 教授 守島基博氏にお願い致しました。
■コーディネータの学習院大学 守島教授
冒頭、守島氏からは、「心身健康経営の時代」と題した現状の課題の整理が行われました。守島氏からは、人材という資源を大切にしてきた日本企業において、今その人材が不足していること、そして働く人々の「仕事そのもの」に対する働きがいが低下しているとの指摘がありました。人材不足については主に流通業、外食産業等で喫緊の課題に挙げられていますが、守島氏の指摘は、人の数が不足しているというより、人材、能力としてどうなのか?を考える必要があるということです。さらに現状の課題としては、メンタルヘルス問題の悪化、職場機能(新入社員の社会化や、協働作業の学び、癒しなど)の毀損があります。こうした中、健康経営への関心が高まっていますが、いまだ心身の総合的な健康という意味では不十分な企業が多く、また健康な人材であっても十分な価値が提供できない人も増えています。このような現状認識から、今こそ、人という資源の量的・質的確保について、これを経営戦略(あるいは小林氏の言う経営改革)のど真ん中において進めていかなければならないのではないか、それを無くしては、「人材倒産」(人的資源の不足のために会社が倒産してしまう事態)が起きてしまうのではないか、との問題提起がなされました。
その後、こうした人材の問題を経営の中核的課題に置かれた2社として、大日本印刷様と、東急電鉄様のお話を伺いました。まず、2社より、それぞれ20分程度で取り組み内容をご紹介いただきました。
■大日本印刷株式会社 専務取締役 神田徳次氏
大日本印刷様は、受注産業ということもあり、長時間労働が状態化している時代がありました。そこで、2009年から単なる労働時間短縮ではなく、業務プロセス改革も含めて実行し始めました。それにより長時間労働については一息つき、2013年から再スタートを切りました。そこからは人材が働きがいを持てるための改革を進めています。同社は他にダイバーシティ推進や働き方の変革というテーマを持っているため、健康いきいき職場づくりはそれらと統合して進めています。具体的には、ストレスチェックの仕組みを活用し、職場向けに「働き方の変革」として、全職場(一部生産職場を除く)で職場の現状分析をし、ゴールイメージ(ありたい姿)を共有し、仕事の運用プロセスを見直すことも含めて活動を進めています。その活動事例を全社から集め、GOOD AWARDと称して表彰などもしています。一方で、毎年総合健康リスクが一定以上の数値の職場をハイリスク職場として抽出し、現地調査や対策検討会を実施。また、決められた実行計画をフォローするための定例相談会も行われています。その結果、総合健康リスクや、ワーク・エンゲイジメントの数値は改善しているそうです。今後の課題としては、現状ではまだストレスの高い社員もおられ、心身の健康レベルの向上は必要であること、引き続き働きがいの向上、それによる新しい価値の創造を進めて行かれたいとのことでした。 ■東京急行電鉄 執行役員 村井淳氏
■東京急行電鉄 執行役員 村井淳氏
東京急行電鉄様では、健康経営の取り組みとして、最高健康責任者(CHO)を設置、2016年に健康宣言を発表しました。宣言では社員のみならず、その家族や沿線住民までもが健康増進の対象に謳われています。具体的な取り組みとしては、「体」の健康と「心」の健康と分けて施策展開されています。前者は、交通の安全を守るという絶対の使命がある中、基本的なチェックは実施していますが、それでも生活習慣病などのリスク者もおられ、そうした方々を対象に職場を巻き込んだ180日間のプログラムを提供しています。その取り組みの一つに「まかない飯巡回」というものがあります。駅で働く社員の方々は、各駅の現場で夕食を作って食べているそうです。そのメニューを管理栄養士の方が巡回して視察しています。また、朝型勤務も推進しており、7:30までに出社する社員には東急ポイントが付与されるそうです。「心」の健康については、2010年前後よりワークライフバランス推進やダイバーシティ推進の活動を進めることで、各種制度による働く環境の改革を進めています。一方で、制度があっても使われなければ意味がない中、同社ではその素地となる上司と部下の相互理解促進のため「トークwith」活動として効果的なコミュニケーションの醸成を目指しています。取り組みの本気度を示すべく、管理職の考課視点に「風土醸成」が追加されました。いろいろな施策を展開する際に基本としているのは、「できることからやっていく」ことだそうです。できない人や職場ももちろんありますが、その場合はなぜできないか、どうしたらできるようになるのかを考えているそうです。
続くディスカッションは以下のように発展致しました。
守島教授:こうした活動を「経営の中核に置く」とはどういうことか?経営層の意識をまとめて行くのはどうしたら良いか?
大日本印刷・神田氏:2006年に労使共同宣言を行い、働き方に対しての思想を共通すべく発信した。組合、会社ともにそれぞれが事業活動の発展や心豊かな生活のために役割を果たそうと話した。その方針の下に人事労務施策を下しているので、その点ではすんなり受け入れられているのではないか。一方、トップの認識はあっても他役員がどう思っているかというとバラツキがある。経営数値を持って仕事をしている事業部門のトップでも、巡り巡っては人がそれを成し遂げているということで理解してほしいと思っている。
東急電鉄・村井氏:私が人材戦略室長に着任したのは3年前だが、部署名に戦略とあるとおり、戦略として人事を考えることがスタート。経営戦略の中に落とし込むとは、事業と結びつけて考えることだと思う。仕事として新しい価値を提案するときに、社員自身が働き方を変えなければそうしたことはできないはず。役員間のギャップを埋めるためには、自分と人事部長が事業部長に直接会って話をして、意識を高めてもらっている。当社でのダイバーシティも健康経営も、制度、風土、マインド(個人の気持ち)を一緒に変えようと言っている。この3つをセットに変えていくことで、戦略としてうまく機能しているのではないか。
守島氏:両社とも比較的早く取り組んでおられる。推進体制を組む中で、ここだけは巻き込んでおかないといけない、ということはあるか?(トップを巻き込む、というのは大前提として)
神田氏:一つは本社スタッフを中心に、産業医(精神科医)、社外コンサルタント、EAPも重要なメンバーだ。働き方の改善は以前からやっているが、労使関係をベースにしていることが重要だと思っている。2004年以降、労使で時間資源有効活用プロジェクトとしてずっと継続している会議体もある。また、健保組合も大切だ。健診データを有用に活用できれば、個人への意識づけも高まるのでは、という考え方から、健康情報管理室という組織もある。
守島氏:外部のリソース(コンサル、EAPなど)を使うのは極めて重要だ、という考え方になるか?
神田氏:自社をよくわかってくれている人、という前提ではあるが大変重要だ。また外部講師の方が緊張感を持って聞いてもらえる、など効果があると思っている。
村井氏:働き方改革や健康経営がテーマになってきており、うまく体制が回っているという自負はある。労使関係は非常に重要だ。良い情報も悪い情報も組合が持っている。それらが働き方改革に結びつく。また、2000年前後、経営が厳しくなった時代があり、社内イベント等をカットしたことがあるが、労組はそれを継続してくれていた。それが今につながっているという点は大きい。また、産業医の役割は大きい。鉄道職場を良く理解してくれており、ストレスチェックの調査票もオリジナルを作ってくれている。また、職場との間に立ってくれている管理職も重要。うまく職場を巻き込んで推進している管理職もいるが、そうでない人もいて差は激しい。管理職の対する人事からのサポートとしては、部下からの評価も含め、自分のマネジメントスタイル、コミュニケーションを振り返ってもらう機会を設けている。
守島氏:今の話は重要だと思う。こういう活動においては中間管理職の役割が大きいが、大日本印刷様では人事としてサポートしていることはあるか。
神田氏:働き方改革、健康経営というテーマでは、事業部門のスタッフを通じた支援をしている。事業部毎に専任の事務局を置いて、ラインへの支援を行っている。ただ管理職の能力のばらつきについて平準化できているかといえば難しい。
守島氏:事業毎の総務や人事もこの活動の中に巻き込んでいる、ということ。
守島氏:それではここで、フロアから質問を伺いたいと思う。何か質問がある方がいらっしゃればどうぞ。
ご参加者A氏:働き方の変革について、取り組まれておられる中ですごいと思うのが、しっかり「やりきっている」ことだ。その秘訣があったら教えてほしい。
神田氏:そこが一番ミソの部分だと思う。継続的にラインに続けてもらうのには仕掛けが必要だと思う。当社では2013年の再スタートの際にギアチェンジをした。2013年からはトップに出てもらい、トップセミナーを実施した。本社だけでなく地方にも出て行ってもらった。その様子はDVDにして活用した。それ以前はスタッフの地道な努力だと思う。事業場にも直接出向いて、事業部長と直接やりとりをすることは重要だった。それが続いて根付いたのではないか。
村井氏:初めからデザインして進めているわけではく、各職場にそれぞれで考えてもらっている。自分の考えることが実現するのは嬉しいこと。例えば職場に体重計を置く、自動販売機の中身をお茶中心にする、などのアイディアをちゃんと取り入れている。また、各職場何をやっているのかをトップ自ら知り、その上で褒めてあげることが効果的だ。
守島氏:結果を見える化する、というのはとても重要なアクションだと思う。例えばDNPさんでは改善率を掲げている。また、外部評価の賞などに応募してもらってくる、というのも重要だ。それも結果を見える化することの一つだ。
参加者B氏:100人くらいの小さい会社であり、ストレスチェックをこれからやろうとしている。既に何人か精神疾患に罹患している者もいるが、そういう社員を排除するのではなく、仲間として一緒にやろうと思っている。何とか発病する前に戻ってほしいという思いがあるが、どうしたら良いか。
川上氏:産業医の立場から申し上げると、職場のメンタルヘルスは今、「愛と法律」でできていると思う。法律で決められた対応をする側面と、職場に戻ってほしいと思うように、愛を持って対応する側面がある。例えば統合失調症の方がいて、その方が職場で働くためにどういう方法を採ったら良いか、例えば仕事に集中するためにはどうしたら良いか、上司の方とどのようにコミュニケーションを採ったら良いかなど、愛を持って職場でデザインできる余地はたくさんある。これから両立支援など、障害を持った方が職場で働くことも増えてくると思う。愛と法律、両方の側面を考えるのが良いと思う。
村井氏:誰でもメンタル不全になる可能性があると考えており、職場の環境の変化などがあると、3カ月くらいでいろいろなことが起きてくると聞いているので、異動して3カ月後の面談などを実施して気にかけている。職場のコミュニケーションについてはいろいろな制約が出てきて希薄化していると思うが、ハラスメントやメンタルヘルスの問題があるので、やはりコミュニケーションを大切にしたいと思っている。
神田氏:ここにいらっしゃる皆さん全員が同じような悩みを抱えながらやっているのだと思う。個別の対応になると思うので、今日のテーマとは異なると思うが、経営レベルで考えれば、一定のルールの中で動かなければならない。ただ、できるだけ一人ひとりの状況に合わせて丁寧に対応することが必要。そのための仕組みづくりは公平・公正でなければならない。
守島氏:きめ細やかに対応する、ということをやっておくと、他の従業員がそれを見ている、ということが大切なのだろうと思う。最後にお二人から、これだけは大切だということをメッセージしてほしい。
神田氏:経営レベルで物事を考えるということと、ライン(職場)でのスタンスはどうしても乖離がでてきてしまうと思う。個別に対応することは大切だが限界がある。やはり、基本的な共通の考え方、基盤を持つことが大切だと考える。この考え方はまわりまわって経営に役に立つのだ、という考え方で制度・仕組みを作ることが大切だと思う。
村井氏:今日のテーマは働き方や健康を経営戦略で考えること。経営に資するものでなければならないことは当然。そのために具体的に何をするのかという点については議論でもふれたが、できるところからやる、ということが大切だと思う。昔は不公平だとか言われることもあったが、今は、個別にやらねばならないことをやっていくことを考えている。人事部門は物事を変えること、否定することに対する抵抗感が強いと思う。それではちょっと、戦略というものを考える時にどうなんだろう、と思っている。
守島氏:お二方とも、今回は大変貴重なお話をありがとうございました。
以上の議論を以って、健康いきいき職場づくりのための経営者シンポジウムは終了いたしました。ご参加アンケートにより、大変興味深かったとお答えいただける方が多数いらっしゃいました。本シンポジウムでいただいた講演、またパネルディスカッションによって、ご参加企業の皆様のお取組みが一歩、二歩と進まれることを祈念しております。
文責:健康いきいき職場づくりフォーラム 事務局