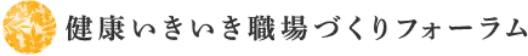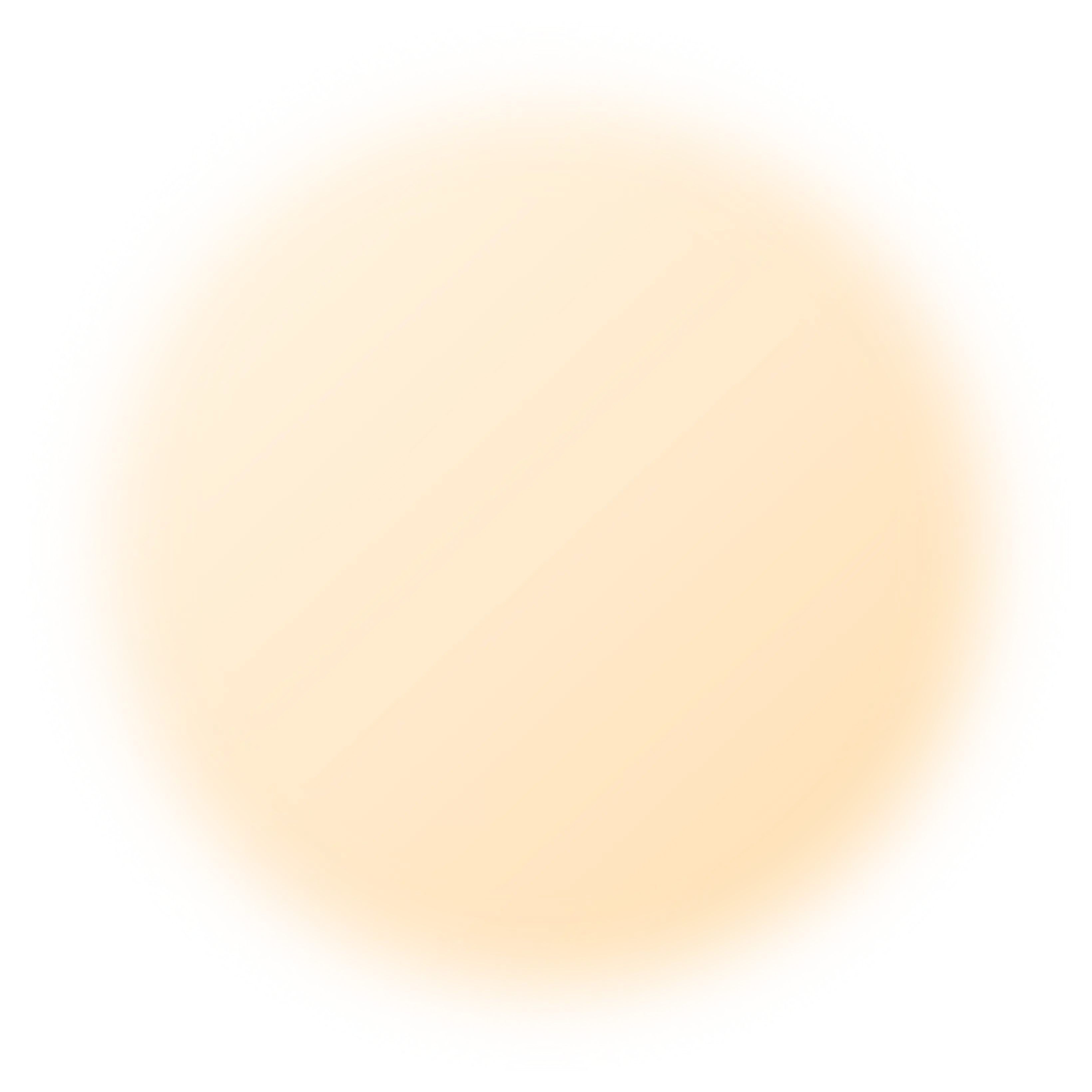去る6月22・23日に、第3期Active Work Place研究会の第2回・第2期研究会の第7回(最終回)を開催しました。本研究会は、約1年間7回にわたる会合を通じ、「健康いきいき職場づくり」の最新理論を学習いただくと同時に、「いきいき職場」実現への、各社での具体的な行動計画策定・その実践を行うことを目的にしております。今回は、第2期・3期の合同開催ということで、2期の成果発表会と3期の実践課題設定を同時に行い、様々な情報交換・共有の場ともなりました。
「これだけ多くの方法論があるということが、健康いきいき職場づくりの道筋の多様性を物語っている」(川上憲人氏)
まず最初に、2期の成果発表が行われました。
①金融系企業(社員数約2000名・名古屋本社)
同社は、近年の急成長を受け、新たな組織文化を構築するために、人事・総務が連携しながら各種施策を講じている点に特徴があります。2009年に出されたトップメッセージ~「仕事を楽しむ」「仕事にやりがいを持つ」「会社にプライドを持つ」~に即し、社員ひとり一人=セルフケア能力の向上、マネジメントサイドへの働きかけ=企業文化変革につながる働きやすい職場環境づくりが行われています。その具体化に向け、ワーク・エンゲイジメント研修、いきいき度診断のフィードバックなど、新入社員サポートから障碍者支援まで各種施策をいきいき施策と連携させ、ロードマップに基づき施策を展開し始めています。同社の施策の特徴は、トップ方針という資源を有効活用できていること、ありたい姿からの具体的な逆引きができていること、取り組みの紐づけ・棚卸ができている点にあるといえます。今後は、人事部門と総務部門のコラボレーションが一層進むことが期待されます。

②IT企業技術開発部門(社員数約11000名・東京本社)
同社はIT業界という高ストレスになりがちな業態において、社内や関連会社でプロジェクトマネジメントを円滑に進めるための支援を行う部門を有しており、今回発表もそこでの支援事例に基づいています。具体的には、ストレスチェック実施を第一ステップとして、その後の職場改善プログラムを第二ステップとして提供しているそうです。今回研究会で得た知見を基に行われた介入では、ストレスチェックの後にファシリテーション研修、職場ディスカッションを行いました。そこでは、ストレスチェック結果の共有やディスカッションによる新たな気づきがある一方、職場特性に合った進め方が求められることが発見されたそうです。同社の取り組みの特徴は、社内コンサルトというある種特殊な状況に合わせて個別具体的なプランニングをしている点、いきいき職場づくりワークショップを活用している点にあるといえます。今後は、職場の構造上の問題にも切り込むためのコンテンツを充実されることが期待されます。
③化学繊維系企業(社員数約10000名・東京本社)
同社は企業規模の割に常勤産業医が少なく、必然的に予防(職場環境改善)・早期発見(個人チェック)に着目する環境にあったそうです。ただ、2003年から開始したストレスチェックでは、設問数の制限や課題着目型の取り組みでもあり、取組み側のモチベーションにつながっていないという問題がありました。そこで、設問数の増加やポジティブアプローチへの転換を2010年以降に行い、具体的には要改善職場へのファシリテーター教育と、そこを起点とした職場改善活動を積極展開しています。ファシリテーター教育では、職場長が指名した中堅クラスのファシリテーターに対し、ストレスチェックの読み方や改善計画の策定法など、実践的な視点での教育が行われます。今後に向けては、次回のストレスチェックでワーク・エンゲイジメントや職場の一体感など、いきいき関連の指標の状況を確認すること、改善活動の事例の蓄積をさらに進めることをしたいとのことでした。同社の取り組みの特徴は、元からの活動にさらにポジティブな視点を加え、それをシステムにまで落とし込んで展開していることにあります。今後は、それを経営活動とも連携していくことが期待されます。
④化学系メーカー(社員数約20000名・東京・大阪本社)
同社は、各所に事業所がるという特性上、メンタル対策も現場任せになっていたのを、2011年の「こころとからだの健康管理方針」を策定し、さらに今年度よりグループで一括して取り組むべく情報管理や取り組み支援の体制を強化しながら進めている状態です。そのため、全社単位では、サポートセンターによるフォロー=未然予防やカウンセリングなどの事業場への支援、ストレス耐性強化プログラムの提供を通じ、フィジカル・メンタル面での健康経営施策の強化を進めています。一方で、事業所単位では、今回事例の事業所のように、事業所トップを起点とした、より価値ある仕事に取り組むための時短実践や業務改善、ボトムアップ型の美点賞賛活動など、それぞれの実態に合った施策を展開しています。同社の取り組みの特徴は、経営の視点での取り組むために体制を再編している点と、一方で現場単位ではより具体的な施策を展開している点にあります。今後は、ポジティブな視点をさらに強化し、経営に資することをもっと発信しながら展開していくことが期待されます。
続いて、3期の実践課題が発表されました。実践課題は、個人レベル・組織レベルで、それぞれ1年後にどういう状態を実現したいかを、定量・定性面でまとめてもらいました。
①化学品メーカー(社員数約500名・京都本社)
同社は労使で取り組みを進めていることが特色で、今回は人事・保健師・労組がメンバーに入っています。そこで、取り組みも現在進めている職場ドックや研修体系の有効活用やそのブラッシュアップ、ポジティブな観点の一層の導入などが課題として挙げられました。
②リハビリテーション病院(職員数約400名・東京本社)
同組織はリハビリテーション病院という特殊な形態でもあり、一般的な人事総務の仕組みは当てはまりにくいため、実績を上げることが大事という認識があるそうです。そこで、病院の目標の一つとして「働きやすい職場の実践、そのための人財養成」を掲げ、スターター認証などによる具現化のために研究会を活用するという形を取りました。
③化学品メーカー労組(社員数約30000名・東京本社)
労組という立場での参加ということで、経営との連携、現場での活動両面を視野に入れ、本部だけではなく、実際に活動を推進している各支部のメンバーにも参加してもらっております。今後の方向性として、会議体の充実やさらなる連携、具体的には労組とゆかりのある産業保健スタッフを巻き込みたいという課題設定がなされました。
④化学品メーカー工場部門(社員数3500名・東京本社)
昨年度スターター認証を取得したことを受け、そこで定めた取り組み計画を労使で実践していくために改めて勉強するために参加したとのことでした。実際に各職場レベルでそれを具体化し、よいアイディアを自分たちで出せる職場にし、資源を高められるようにすることを課題にされました。
総括として、東京大学の川上憲人教授より、「2・3期ともに取り組みが非常にバラエティに富んでおり、統一的な総括は難しいが、それがいきいき職場づくりの奥深さを物語るものではないか。しかし、「いきいき職場づくりを大切にする」という信念はぜひ共有してほしい」というコメントがありました。
終了後、2・3期の懇親会・情報交換会を催し、実践に向けての意識づけ、さらなる学びの場に向けての提案、取り組む上の苦労についての質問など、時を忘れて多くのやり取りがなされました。
「非常に具体的な資源が多く上がっていすね」(島津明人氏)
二日目は、3期の第2回として開催されました。健康いきいき職場づくりを進めるうえでの重要概念である「ワーク・エンゲイジメント」(以下WE)や、それを職場で高めるための管理者教育の新たな方法論、職場資源の棚卸などを行いました。
まず、WEについて、東京大学の島津准教授よりレクチャーがありました。WEは、「仕事に誇りを感じ、熱心に取り組み、仕事から活力を得て活き活きしている状態」と定義され、ワーカホリックやバーンアウトとは区別されるものです。これが高まることで、身体面の健康の向上や、上司から部下への伝播などが見込めるため、各種資源が高めることが重要だとされています。そのために、上司のマネジメントによる向上、仕事の意味づけの変化による向上(ジョブ・クラフティング)など、多くの方法論が現在模索されています。
続いて、東京大学の関屋特任研究員より「HSE(英国健康安全局)のマネジメントコンピテンシーリストを用いた管理監督者研修の進め方」と題し、英国で活用されるリストを活用した実際の管理者向け教育の体験講座が行われました。島津氏の講義にもあったように上司の果たす役割は重要であり、その上司がよりよいふるまいをすることによる効果を狙ったのが同研修プログラムです。ここでは、上司のコンピテンシーを「部下への配慮と責任」「現在と将来の仕事に対する適切な管理・伝達」「チームメンバーへの積極的な関わり」「困難な状況における合理的な考えと対処」として、自己評価式での判定をきっかけにしながら、研修参加者(マネージャークラス)同士でのワークショップにより、自身のマネジメントスタイルの見直しや相互学習を促進することを目指しており、既存のラインケア研修のように不調者が出ないと使えないものではなく、普段から活用できるのが最大の特徴だとされています。

さらに、島津氏より「組織の強みに注目した健康いきいき職場づくり」と題し、ストレスチェックなどのアセスメントを起点とした職場環境改善の方法論の概要が示されました。改正労働安全衛生法の改正でも、ストレスチェックは「生産性の向上」「事業経営の一環として」行うことが要請されており、これは問題探し型の観点とは異なると島津氏は述べます。実際に、ストレスチェックを基に、当該事業所の強み・課題(弱みや問題(Problem)ではなく、挑戦課題(Challenge)を検討し、それを働きやすさ軸、働きがい軸に基づき、着手しやすさ、モチベーションが上がるものになることを加味して設定するという方式があるそうです。事務局は、取り組みのモニタリングと励まし、進捗報告シートや中間報告会を活用した好事例の共有などを通じ、現場での取り組みを支援することが要請されます。
最後に、これまでの事例や「資源」強化の方法論を基に、各組織に分かれ、自組織の有する資源や、今後高めたい資源をピックアップし、それを共有するワークを行いました。ここで共有された資源を基に、各職場で今後高めたい資源を確認するワークを次回以降行い、最終的に行動計画に落とし込みます。島津先生のコメントによると、今期は非常に具体的な資源が上がっており、より現場活動に密着した行動計画が期待できるとのことでした。
次回は8月25日(火)に開催され、そこでは今回課題である自職場のアセスメント結果、資源ピックアップの共有の後、「強み」に着目したワークとしての「AI」の体験を行います。