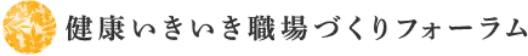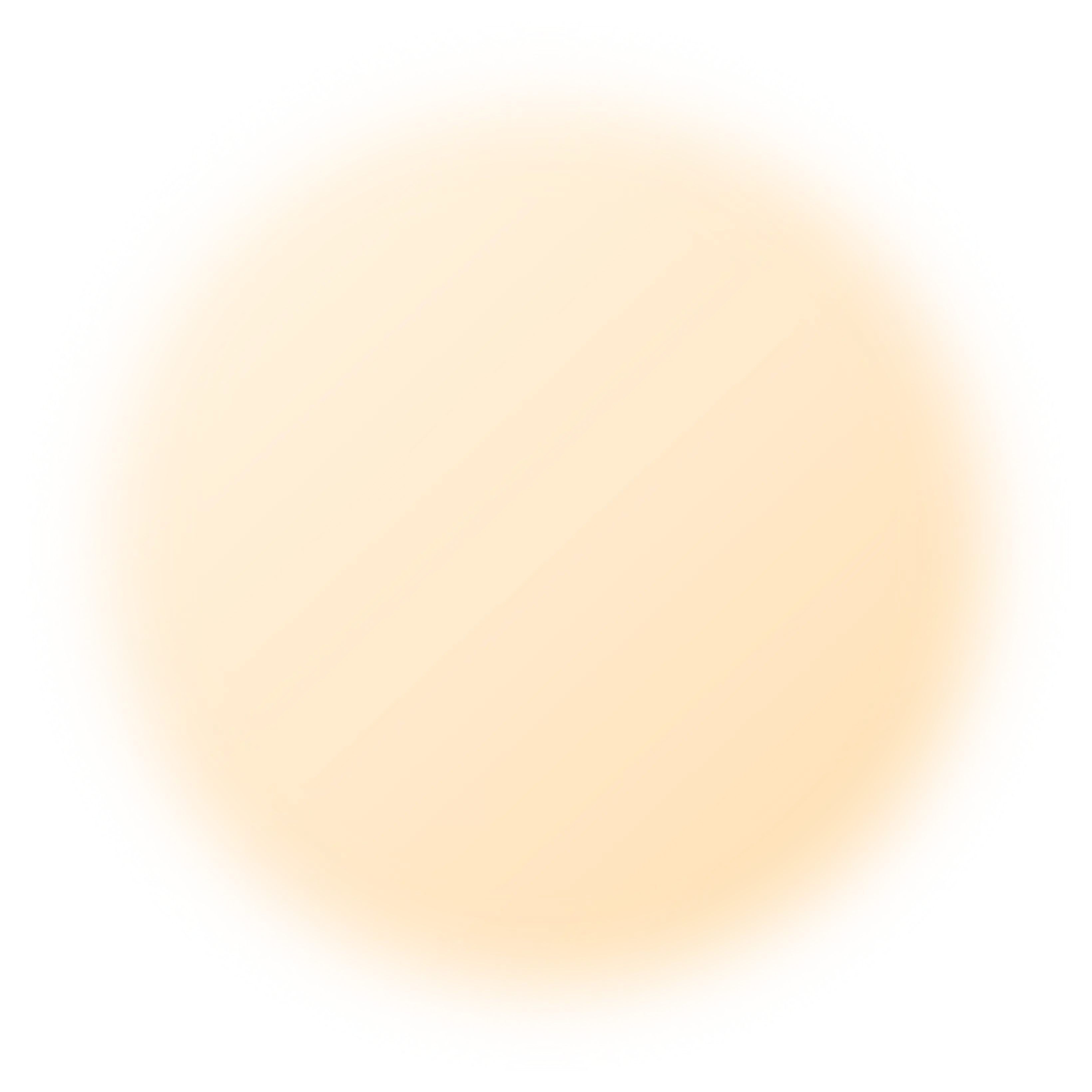去る5月25日に、第3期Active Work Place研究会の第1回を開催しました。本研究会は、約1年間7回にわたる会合を通じ、「健康いきいき職場づくり」の最新理論を学習いただくと同時に、「いきいき職場」実現への、各社での具体的な行動計画策定・その実践を行うことを目的にしております。初回である今回は、参加4組織の問題意識の確認や、いきいき職場づくりの理論的背景の理解を目指し、白熱した議論が行われました。
「健康いきいき職場づくりは新しいメンタルヘルス対策であり、新しい経営戦略である」
(川上憲人氏)
まず最初に、東京大学大学院教授の川上憲人先生より、「健康いきいき職場づくりとは」と題して、総論講義が行われました。その中で、川上氏は、健康いきいき職場づくりは、新しいメンタルヘルス対策としてだけではなく、新しい経営戦略として行われることが案内されました。その背景として、我が国のメンタルヘルス対策の変容(リスクマネジメントからポジティブへ)、理論的背景の変化(健康障害モデル=「負担を減らす」から「資源を増やす」へ、ワーク・エンゲイジメント、mental wellbeing、心理的資本、各単位での社会的・心理的資源の重要性など)、取り組み主体の変化(ヘルスセクターからノンヘルスセクター(ビジネスセクター=人事、経営企画、労組など)との連携)などがあるとのことです。

また、昨年当フォーラムで策定した「健康いきいき職場づくりガイダンス」に即して、準備段階(①関係者の組織的関与の確保②推進主体の設置③ビジョン策定④周知方法の検討)、実践段階(⑤組織の多面的評価⑥いきいき職場づくりの計画立案⑦計画実行・フォローアップ)、展開段階(⑧さらなる展開)の各段階での検討事項やトライアンドエラーの重要性、、いきいき職場づくりの教科書である『健康いきいき職場づくり』より、実践事例の紹介が行われました。さらに、従前の心の健康づくり計画の有効活用や、12月施行の改正労働安全衛生法の積極展開の重要性、いきいき職場づくりの可能性(こころの健康の保持増進、生産性向上、企業の維持発展、労働者の幸福実現、企業規模を問わない発展など)も触れられました。また、当研究会は双方向のコミュニケーションが特色です。講義に関しての疑問点、確認点なども、多くの時間を取って行われました。
(主な質問事項)
・「仕事の資源」という用語は難しいが、どう説明すればよい?
・「いきいき職場づくり」の経営への訴求方法は?
・志向が多様化しており、人とのかかわりを嫌がる人も出ているので、資源にならないかもしれないのだが?
様々な問題意識~巻き込み、認証の具現化、体制づくり、2次予防から1次予防へ・・・~
続いて、参加4組織による自己紹介と事前課題である参加理由、現在の体制についての説明・実践方法などに関する質疑応答が、参加者間や、コーディネーターである川上氏、東京大学大学院准教授の島津明人先生も交えて、活発に行われました。
A労組)
・「働きがいと生きがい」をキーワードに労使での取組や職場自治活動を進めているが、最近、「問題意識はあるが当事者意識はないケース」や、労使の施策として掲げている「働き方改革」の浸透の薄さ、ストレスチェックの活用法で総論賛成だが具体的な動きが鈍いなどの悩みを抱えている。それを少しでも改善し、組合員や会社の関連部門をより巻き込むためのヒントを求めて参加した。
B社X工場)
・昨年度「健康いきいき職場スターター認証」を取得した。幸い、工場長の理解が高く、推進委員会での発信や従業員の理解も進んできたが、推進委員会の具体黄な活動はまだまだで、職場環境改善、ワークショップなどの展開方法はこれからいう状況にあるので、今後本認証を目指すに際し、「いきいき」の理解を深め、推進のためのヒントを得たいという思いで参加した。
C社)
・昨年度東京都のワーク・ライフ・バランスのワークショップに参加し、そこで見えてきたものをさらに活用したいと考えている。具体的には、「職員が働きやすい職場の実践」を組織目標に入れた。また、機能評価の項目にも人事やメンタルに関する項目があるので、研究会参加内容を活用したい。ただ、一部部門は非常に離職率が高いという現実や、体制図はむしろ具体化していくというレベルで、組織内に取り組みを進めるための仲間をもっと増やしたいといいう動機もある。
D社)
・当社は、幸い離職者は少なかったが、最近メンタル疾患がやや増えてきた。実施したストレスチェックでの課題も見えてきたので、それを人事施策に生かしたい。具体的には、「効果のある1次予防の実施」「職種に合わせた環境改善」「ポジティブ心理学の企業内研修への応用」を目指したい。当社は、社員・経営の信頼関係が高く、離職率も低く、健康管理体制も充実しているが、一方で新経営陣との対話や社員像の不明確さ、メンタル対策中期計画の策定などを抱えている。これらをより良い形で進めるために研究会を活用したい。

「いきいき職場づくり」とは職場機能の改善であり、むしろ経営活動である」(守島基博氏)
続いて、一橋大学大学院教授の守島基博先生より、「企業競争力の原点としての“健康な”職場~経営視点から職場を考える」として、経営学の観点からの「いきいき職場」の捉え方について講義が行われました。
守島氏は、経営という観点での職場機能には、「協働」「人材育成」「所属」「同質化(社会化)」の機能があり、それが企業活動の源泉となっていたのが、近年徐々に衰退してきた現実があるとします。その結果、「職場寒冷化」現象が発生し、様々なひずみを発生させるとともに、それが結果としてメンタルヘルスにも悪影響を及ぼしたと説明されました。そのため、職場機能の低下という問題は、実はメンタルの問題ではなく、経営の問題としてとらえてもらう必要があると述べます。そして、経営視点での職場では、「チームワークによる大きな目標達成ができる」「人材育成ができる」「コミュニティとして癒し・安心が得られる」ことが期待され、これこそが「いきいき職場」につながるとしています。

そして、その解決のためには、職場機能回復のための組織開発的視点、具体的には
①育成型職場を作る(OJTの戦略化、体系化)
②リーダー支援(リーダー力の底上げ、フォロワーの育成)
③モチベーションを高める(達成感、成長につながるフィードバック)
④絆のある職場(人と人とのつながり、コミュニティとして)
が重要であり、強いつながりを持つ職場がすべての起点になるとまとめられました。
これを受け、後半では3グループに分かれ、「1 皆様の職場は「健康な」職場か」「2 そうでない場合、どうすれば健康になるか」という観点での議論が行われました。守島先生による巧みなファシリテーションもあって、いよいよ、いきいき職場づくり実現に向けてのより具体的なイメージがもたらされてきました。


(グループ内での主な意見)
・垣根を超える、本音でぶつかり合いができるのが大事。聞けば本音はでる
・従業員の話を聞く場を設ける-経営への参画感へ
・業務調整や手順書づくりで情報共有
・上位組織からの指示をかわすことで、余計な仕事を抱え込まない
・ポータルサイト・社内報の活用
・レクリエーションを増やす
・個の方向性・目線を合わせる
・トップとの直接懇談
・一人一人に活動の意義(メリット)を示す=同志を増やす
・自分語りから入る=相互理解
・まずは成功事例を一度味わうことから
これらの意見に対して、守島氏からは「ぶつかり合い」と「本音を言える」をどう両立させるかや、成功事例を意図的戦略的につくることの重要性について言及がありました。また、「いきいき」を単なる「優しい言葉」ではなく、それともビジネス用語として説明することの大切さも触れられました。
この後、次回第2回(6月22・23日・第2期との合同開催)に向けての事前課題の説明が行われ、さらには懇親会を通じ、1年間歩みをともにするメンバー同士の絆づくりが行われました。