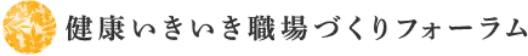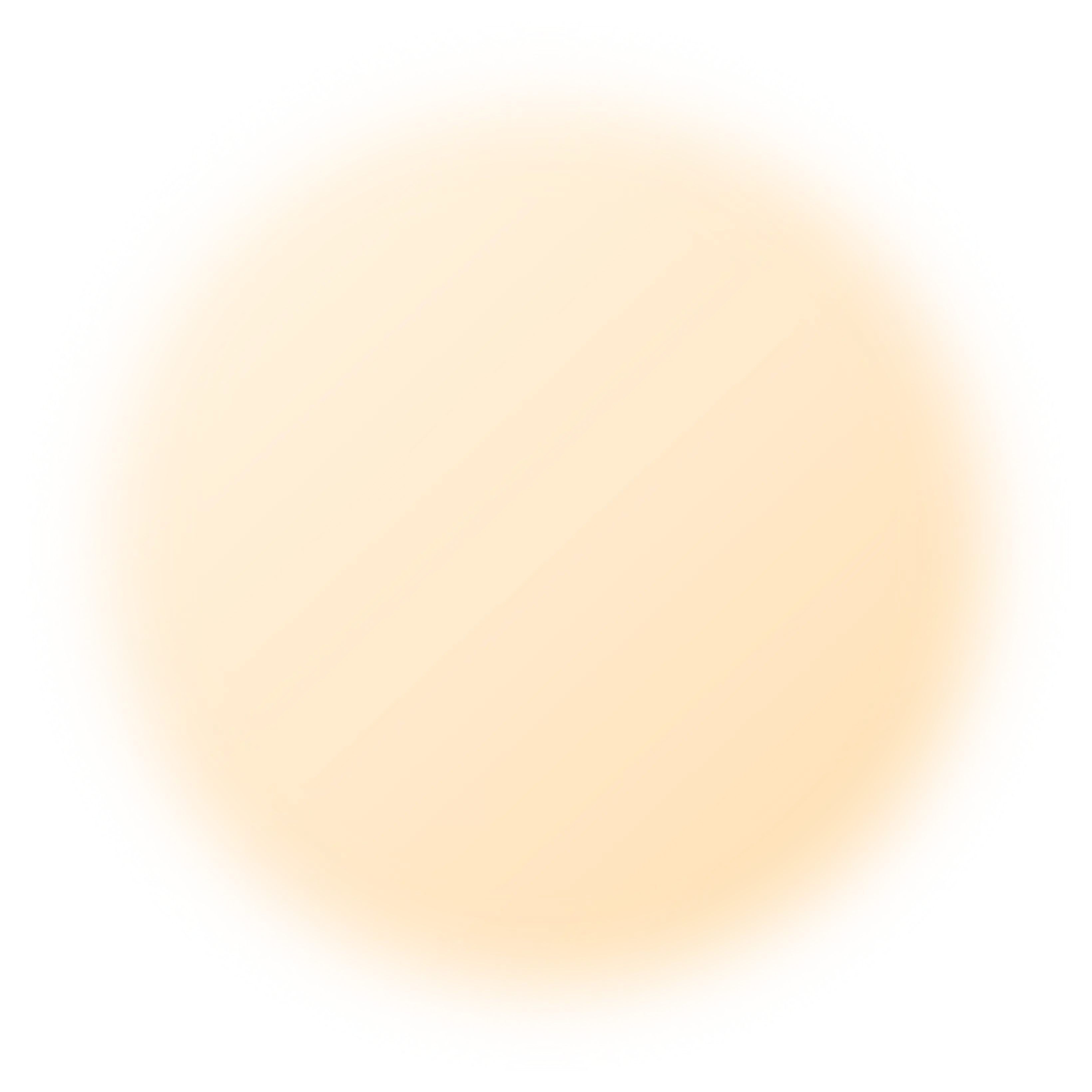去る2月23日に、Active Work Place研究会第6回を開催しました。今回は、いつもの渋谷の生産性ビルを出て、参加メンバーの1つである名古屋の金融業を中心とする会社のオフィスにお邪魔して開催しました。今回は、前半で訪問企業での取り組み事例や施設見学、後半で策定した行動計画の中間振り返りを実施しました。
今回は、通常回とは異なり、訪問企業の取り組みを案内いただくことから回はスタートしました。同社は、この数年来の会社の拡大に合わせ、企業文化を変革すべく、2009年に、「フェアネス」「多様性」「人材育成」を軸とした人材マネジメント方針を掲げました。そして、社長からのトップメッセージとして、「人を大切にする」を掲げ、単にやさしいということだけではなく、社員には主体性を、マネジメントにはそのための環境を提供することを求めています。そのために、「対話」を軸とした様々な活動を現在進行形で進めています。
その際の体制として、総務部(健康推進G)と人事部が連携して、推進しているそうです。健康推進Gは、新入社員や異動者のサポート、いきいき度診断とそのフィードバック、活性化ワークショップやストレッチなど・・・多様な取り組みを通じ、ヘルスマネジメントと人材マネジメントを相互に行っているのが、同社の特徴と言えます。
また、同社はオフィススペースも工夫をしています。例えば、オープンな会議室、休憩スペースも色遣いを工夫し、またその場でミーティングができる仕掛け、書籍コーナー、リラクセーションスペース、「健康いきいき職場づくり」をはじめんとする各種アナウンスを図るためのポスターなどなど、施設面で健康いきいき職場をサポートしているのも特徴です。

さて、取組み紹介や施設見学の後は、第5回で発表された、今後組織的にどのように健康いきいき職場づくりの活動を展開して行くかを示す、「行動計画」の取組状況を発表いただきました。行動計画は、策定はあくまでスタートであり、そのあとの取り組みが重要です。今回は、前回11月いう工での進捗と、苦労している点などを共有し、相互アドバイスすることで、さらなるブラッシュアップを行いました。
会の進行は、行動計画の進捗を各社よりご発表いただき、島津先生やメンバーからも質問やコメントを受ける形で、様々な視点からの意見交換がなされました。
行動計画は、実施計画とその時期をまとめてもらっております。参加4組織では、実施する取り組み自体を変更する会社はありませんでしたが、実施対象やその時期が様々な事情によって変更を余儀なくされるケースも出ていました。例えば、ある会社では取り組みを進める対象としていた部署がトラブルを抱えたため、いきいき職場づくりを縮小せざるを得なくなったケースがありました。また、ある会社では体制が変わることで、取り組みの見直しを図るケースもありました。ただ、これは逆に捉えれば、いきいき職場づくりの取り組みが、健康管理分野などで独立して進むのではなく、まさに組織ぐるみで推進させるゆえのジレンマとも言えます。
また、ある会社では今回研究会参加を機に、全社の健康支援Gの体制や取り組みを見直し、そこに健康いきいき職場づくりのエッセンスを含めるべく、ワーク・エンゲイジメントやトップダウンとボトムアップの連携を図るようにしたそうです。ある会社では、現場での職場改善活動を重視しつつも、現場の活動だけでは解決が困難な構造改革に伴う大規模な変動に対しては、過度な介入は避けるようにするなど、きめ細やかな対応に努めていることが報告されました。
メンバーからの報告に対して、島津先生からのコメントとしては、評価は定性と定量を、成果とプロセスの両面を考慮することが重要であること、職場改善活動の際には「ありたい姿」への落とし込みを重視すること、労基署による長時間労働是正命令などの危機を改革につなげること、取組み推進の際には好事例の収集・発信機能を大切にすること、社員への取組浸透のために、Eラーニングと集合研修を組み合わせる効用など、様々な観点からのアドバイスをいただきました。
前述したように、いきいき職場づくりの活動は、組織の置かれた状況や時間軸によって、多様な形が考えられます。そのため、活動それ自体には完成形はなく、組織に合った方法論があることが取り組みの中で見えてきました。そのため、当研究会や同フォーラムでは、様々な好事例を収集・発信することを通じ、「これなら我々の組織でもできそうだ」と思ってもらえることを目指します。そういった活動を通じ、業種業態規模を超えて、「健康いきいき職場づくり」の輪が広がっていくことを目標としていきます。
次回はいよいよ最終回、6月22日(月)、成果発表会とともに、第3期との交流会を開催する予定です。