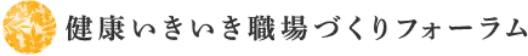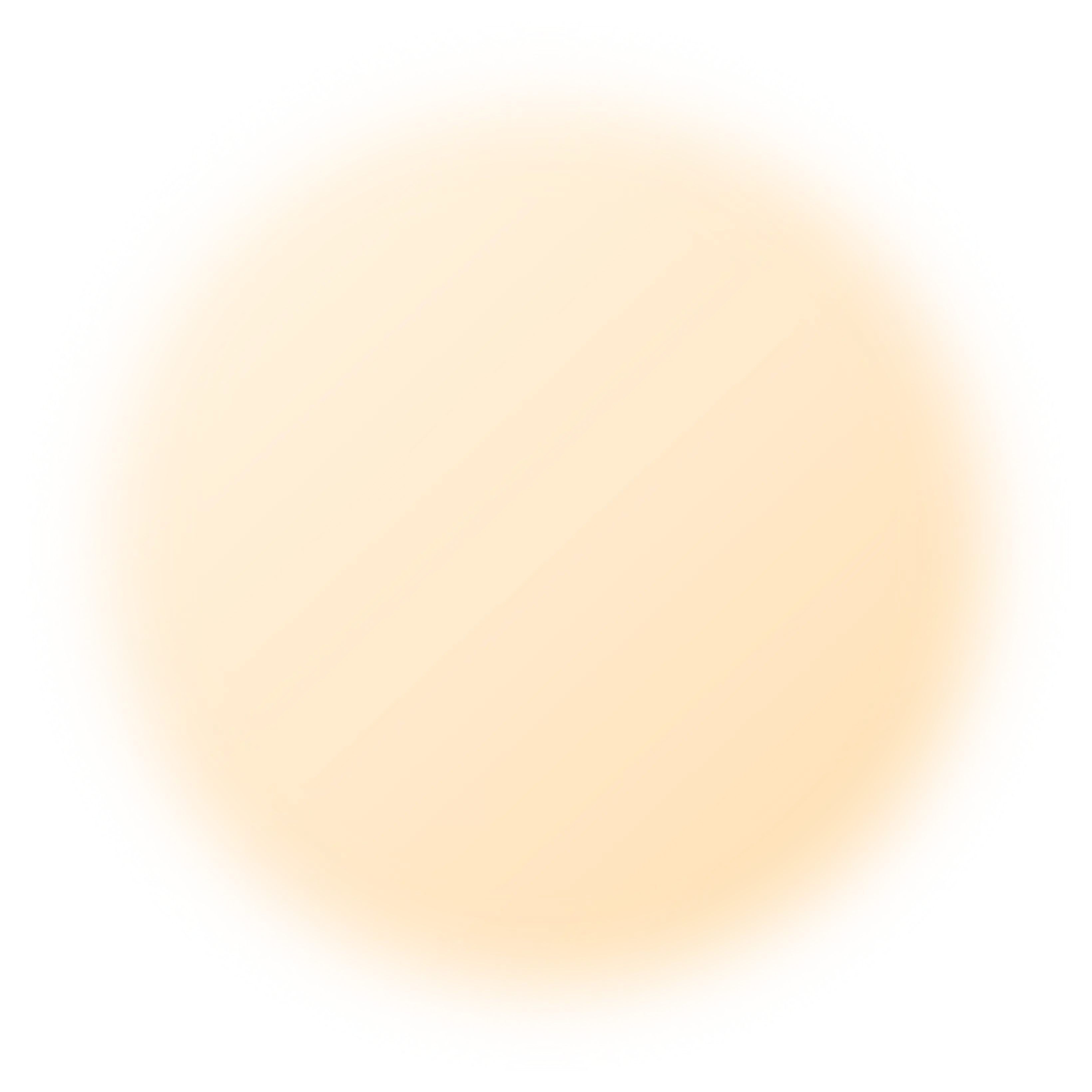2015年2月3日、健康いきいき職場づくりフォーラム定例セミナー「健康いきいき職場づくり ~現場発 組織変革のすすめ~」出版記念が開催されました。
今回は去る12月に刊行された、いきいき職場づくりの「教科書」である書籍「健康いきいき職場づくり ~現場発 組織変革のすすめ~」の執筆者4名と事例紹介として太陽工業株式会社様にご登壇いただきました。
一橋大学大学院の守島基博教授からは冒頭、本書に掲載された座談会の概要と問題意識が紹介されました。ポイントは以下の4点です。
1. 日本の職場で何が起きているか。
2. 経営トップに、如何に理解を求めていくか。
3. フォーラム2年の経験から学んだこと
4. 今後の方向性
上記4点を通じて言えることは、運動は経営トップを巻き込むことが重要であり、それが力になる。そのためにも、いわゆるメンタルヘルスの改善だけでは不十分であり、経営の視点をもって「人が働きたくなる組織、働きやすさと働き甲斐を兼ね備えた組織をつくる必要がある、というものでした。
東京大学大学院の川上憲人教授から本書の位置づけと今後の課題、昨年末に表彰式を行った「スターター認証制度の活用法」などについて、お話がありました。
川上教授は、本書を日本初の教科書的存在のものと位置づけ、これからの本運動を後押ししてくれるものと紹介されました。一方で、この2年間の活動の中で見えてきた「矛盾」のようなものもあり、今後の課題と位置づけ検討を進めると話されました。
今後の大きな課題として紹介されたのが、健康いきいき職場づくりがメンタルヘルス対策なのか、経営戦略なのかという立ち位置の問題です。従来から経営戦略の一部として考えようとしてきてはいますが、実はどちらでも構わない話であって、どちらからのアプローチであっても「健康いきいき職場づくり」が目指す職場の実現につながればいいのではないかとのことでした。
その上で、更なる課題として提起されたのが「健康いきいき推進委員会(仮称)」の設置と健康いきいき職場づくりの周知方法です。前者は「健康いきいき職場づくりの8つのステップ」の中のステップ2、後者はステップ4に位置付けられています。企業・組織の中でこの運動を組織的に、そして効果的に展開するためにも不可欠なことであり、特に後者についてはスターター認証制度を上手に使ってほしいとのお話がありました。
また、今後義務化される「ストレスチェック」についても、「いきいき=職場環境づくり」につなげてほしいのとお話がありました。
大阪府立大学大学院の北居明教授からは組織開発の考え方とこれからの方向性について、お話がありました。
組織開発は様々な階層を巻き込んで行う取り組みであり、通常、診断型と対話型に分かれます。両者は排他的なものではありませんが、今回は対話型組織開発に焦点を当ててお話をいただきました。
対話型組織開発では、組織を問題解決の対象ではなく、可能性の源泉と考えます。メンバーが自律的・主体的に関わり「どうしたら組織がよくなるか」を考えます。様々な手法が開発されていますが、今回はAI(Appreciative Inquiry)活用のポイントのお話がありました。
1980年代にアメリカではじめられたAIは、組織全体に働きかけ、組織の人的プロセス(コミュニケーション、チームワーク、組織風土など)の改善を目的としたものです。昨今では学校、病院、自治体などでも活用されています。
AIは人的プロセスにアプローチするので、「問い」が重要となります。AIの問いは、一見ネガティブな問題をポジティブな視点で捉え直した上で問い、体験(ナラティブ:Narrative)を語ってもらい、その中から可能性や理想に注目していきます。
AIはこの問いのプロセスを通じて4D(Discovery-Dream-Design-Destiny)サイクルを回し、具体的なアクションにつなげていきます。
東京大学大学院の島津明人准教授からは、ワークエンゲイジメントに注目した組織と個人の活性化について、と題しお話がありました。
冒頭、これまでのメンタルヘルス対策とこれからの対策の違いが明示され、これからは健康管理スタッフと人事担当部門が別々に動くのではなく、お互いに歩み寄り協働することが必要と提起されました。そして、よりポジティブにメンタルヘルスをとらえるにあたり有効とされる新しい考え方「ワークエンゲイジメント」が紹介されました。
ワークエンゲイジメントは、その提唱者であるシャウフェリ教授(ユトレヒト大学)によれば
1. 仕事にやりがいを感じ
2. 熱心に取り組み
3. 仕事から活力を得て活き活きしている状態
とされています。これは、仕事に対してその重要性を認識し、現実的な目標設定を行い、仕事を楽しみ、有意義と感じることから生まれます。結果、“I want to work.”という意識につながります。
このワークエンゲイジメントは、個人や仕事の中にある資源の充実と有意な関係にあるといわれています。つまり、メンバー間の信頼関係や支援のあり方、個人の尊重、役割の明確さ、人事評価などの資源が良好なものになるほど、ワークエンゲイジメントは高まります。
また、個人の尊重が疎かになると「冷たい職場」になってしまいます。職場がそのような状態にならないようにするためのプログラムとしてCREW(Civility , Respect , & Engagement in the workplace)プログラムも開発されていることも紹介されました。
最後に、健康いきいき職場づくりに向け必要なこととして産業保健と経営との協調、トップダウンとボトムアップのバランス、組織の強みを伸ばす(+弱みを克服する)、スモールステップ(できることをできることから取り組む)が提示されました。
事例紹介としてご登壇いただいた太陽工業株式会社様からは、「太陽工業が進める組織開発の実践~組織開発と戦略と利益~」と題するお話をいただきました。
取り組みは、できないことに焦点を当てるギャップアプローチではなく、できていることに焦点を当てるポジティブアプローチで展開するというAIを活用したものでした。ミーティングを通じて採択された行動宣言文やそこから生まれたチームの富士登山への取り組みなど、組織が一体となり、一人一人が元気になっていく様子が、ビデオなども交えながら紹介されました。もともとは赤字体質からの脱却を目指しての取り組み。取り組みの過程で浮き沈みはあったものの、沈んだ時に組織のミッションの重要性を感じそこに話を戻したことで、組織開発が業績につながりつつある。この現状は、健康いきいき職場づくりが企業の成長につながる期待を示してくれるもので、参加された方々の興味を大いに引くものとなりました。
会員の方は、メニューより会員ログイン後に質疑応答と当日の資料をご覧いただくことが可能です。
続きは個人会員 / 協賛会員 / 組織会員 / AWP研究科同窓会組織のみ、閲覧可能です。
会員ログイン