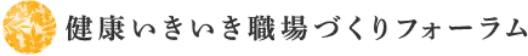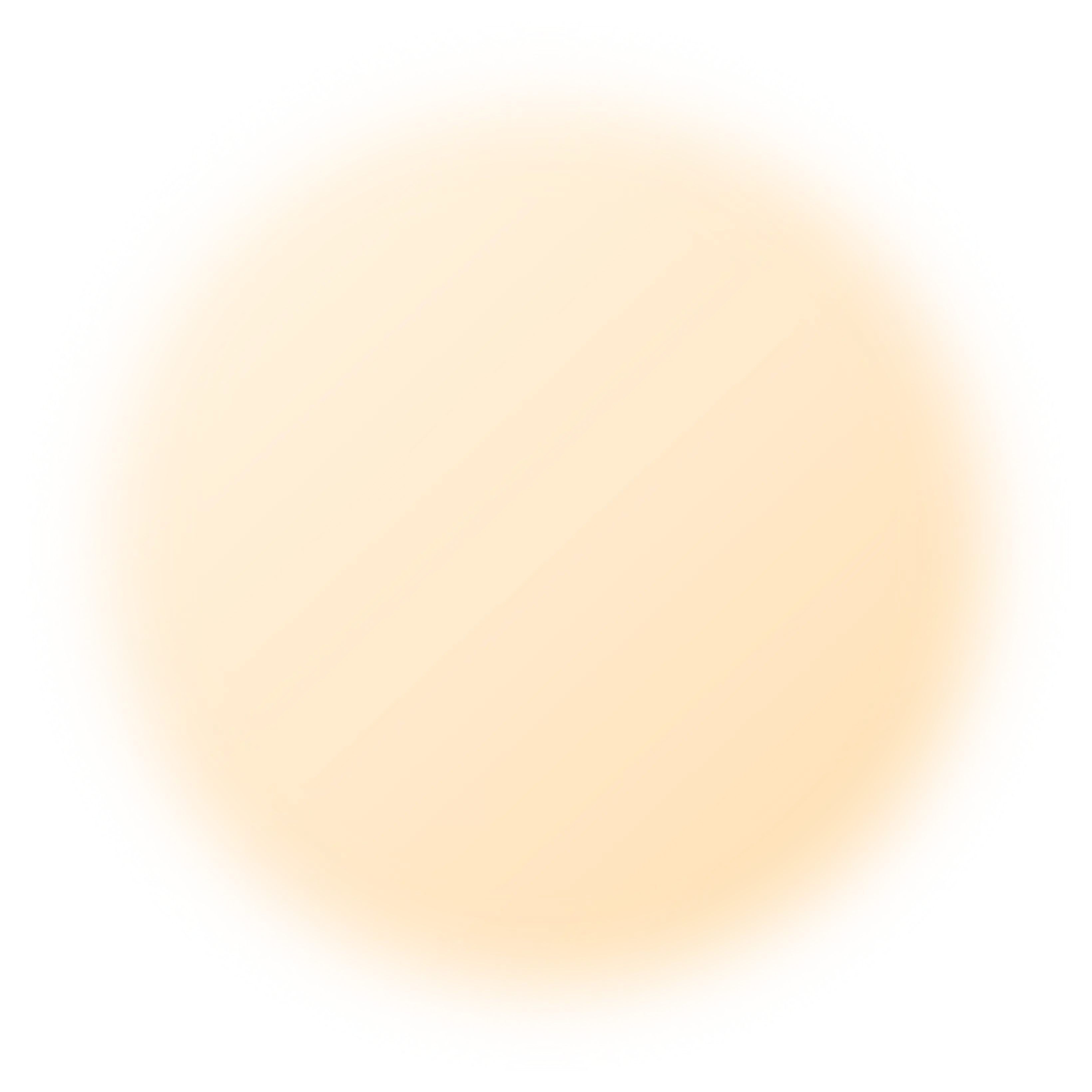2014年10月20日、健康いきいき職場づくりフォーラム定例セミナー「健康いきいき職場最新理論~上司VS部下~」が開催され、多数の方にご参加をいただきました。
今回は「ジョブ・クラフティング」をキーワードに、個人ベースで考えられるアプローチを、「サーバント・リーダーシップ」をキーワードに、職場リーダーからのアプローチをそれぞれ検討していく構成としました。前者については、学識の研究として武蔵大学経済学部准教授の森永雄太先生に、企業人としての実践事例としては、株式会社フジクラ健康経営推進室副室長の浅野健一郎氏より、後者については、福岡大学人文学部准教授の池田浩先生よりお話をいただき、最後に解説・質疑応答として、登壇者と、東京大学大学院准教授の島津明人先生によるパネル討議を行いました。
「職場でいきいきを創り出す「ジョブ・クラフティング」
・ジョブ・クラフティングの解説は、武蔵大学の森永先生より行っていただきました。先生は、「職場でいきいきを創り出す」ための方法論の一つとして、ジョブ・クラフティングがあると定義付けされます。ジョブ・クラフティングとは、「従業員が与えられた仕事の範囲や、他者との関わり方を自ら変えていくこと」です。ワーク・エンゲイジメントを実現するためのジョブ・クラフティングとして、具体的には、仕事の資源(課題多様性、周囲からのサポート、業績へのフィードバック、トレーニングの機会、仕事の裁量権)の充実とともに、個人の資源(自己効力感、組織での自尊心、楽観性)を高めることも重要だと述べます。経営学においても、従来の効率性とともに、従業員のいきいきも重視されるようになってきており、「職務特性モデル」(①スキルの多様性(スキルを活用できる)、②タスクアイデンティティ(何をやっているかを理解している)③タスク重要性(仕事の重要性)、④自律性(マニュアル化ではない)、⑤仕事から得られるフィードバック(仕事の成果))で表現されるような要素が重要視されるようになっています。これらの職務特性を働く個々人が自分なりにとらえなおし、仕事の範囲や他者との関わり方を変えていくことがジョブ・クラフティングだとされています。その実例としては、東京ディズニーリゾートのカストーディアル、顧客志向のSE・看護師、本屋店員のPOPづくりなど、自分なりに仕事の意味を再確認し、より積極的なコミットを産み出した例があります。
・また、ジョブ・クラフティングのタイプとしては、
①-仕事の資源増(上司にアドバイスを求める、顧客にフィードバックを求める)
②-要求を減らす(負荷を減らす)
③要求を増やす(さらなるチャレンジ(責任、能力発揮への提案))
があるとしています。このうち、②は負担減とともに資源も減ってしまう危険もあり注意が必要です。③は前提として職務の自律性を伴う場合に効果を発揮するとされています。
・具体的にジョブ・クラフティングを促進するには、①個人的に取り組む(職務範囲の見直し、身近なところで行う役割の再定義)、②職場に取り込む(マネジメント上で、お目付け役・サポーターからの働きかけを行う、研修での働きかけを行うなど)が考えられるといいます。また、研修では、実施形式(アクションラーニング方式やペアワークなど)やゴール設定上の工夫、計画-実行を連続させる仕掛け、職種別尺度(チェックリスト)を作って効果測定する、コーチングと連携を図るなど、様々な導入方法があるとお話しいただきました。
「活かし、支え、奉仕するサーバント・リーダーシップ」
・次に、職場リーダーからの視点として、福岡大学の池田先生より、「サーバント・リーダーシップ」についての解説をしていただきました。そもそも、リーダーとは、組織の課題・目標があって、それを実現するための取りまとめ役として存在するのだと池田先生は述べます。従って、リーダーからの一方的な働きかけだけではなく、フォロワーの反応も重要です。また、我々のイメージする理想のリーダー像(どういうリーダーがよいか)と、「リーダーシップ」のイメージ(カリスマ、人の上に立つなど)のかい離があるのではないか、そしてそのようなリーダーシップイメージからのパラダイムシフトとして、「奉仕する」「下から支える」「尽くす」「自己犠牲」といった特徴を持つサーバント・リーダーシップが近年取り上げられるようになったとされています。
・サーバント・リーダーシップについて、提唱者であるグリーンリーフは「真のリーダーはフォロワーに信頼されており、まず人々に奉仕することが先決である」としています。そして前提として、「ビジョンの明示」をすることが重要であり、これなくしては「ただのサーバント(召使い)である」と付言しています。サーバント・リーダーシップの特徴としては、「傾聴」「共感」「癒し」「気づき」「説得」「概念化」「先見性」「執事役」「幹事役」「成長へのコミット」「コミュニティづくり」を挙げられ、その背景には、①倫理性重視、②フォロー・フォロワーの成長優先、③成果やビジョンも重要、があるとされています。これらが機能することにより、個人レベルでは、①リーダーへの信頼を高め、②自律的モチベーション(有能感向上)、③協力行動・支援行動促進、④先取り(プロアクティブ)行動促進、職場レベルでは、①個人レベルの効果の職場集団への波及、②相互支援・協力の風土形成の効果があります。これらは理論レベルにとどまらず、実践レベルでも、星野リゾートグループや新幹線清掃チーム(株式会社JR東日本テクノハート)のような、リーダーの傾聴やビジョンの共有、自職場の役割の再定義などを通じ、メンバーの変化が起きてきたことにサーバント・リーダーシップの例を見出すことができます。
・具体的な実践のためには、①リーダーという役割の再定義(けん引役から支援役へ)②フォロワーを信頼することが重要とされます(ただし、ともすれば個人や個別の事例に寄り添いすぎてしまう危険もあるそうです)。また、サーバント・リーダーシップには、フォロワーの自律性の向上、先取り行動の促進と職場への波及、チーム力向上、既存のけん引型リーダーが苦手な人にも適合した新たなリーダーシップ像としての可能性もあるとのことでした。
「私のジョブ・クラフティング法」
・次に、ジョブ・クラフティングの実践例として、株式会社フジクラの浅野氏のお話を伺いました。浅野氏は、高校時代からの登山経験を通じ、ジョブ・クラフティングを行ってきたと述べます。例えば、食事当番は過酷でマニュアルに沿った対応だけではできないが、この中でいかにおいしく食事をしてもらうかにジョブ・クラフティングを見出していました。また、高校時代の山岳部は、登山以外はひたすらトレーニングする日々でしたが、そこでは内的な喜びを見つける(打倒、陸上部・ラグビー部など)ことが継続に通じ、それが結果として登山にも役立ったそうです。そのほか、登山のリーダーになった際には、命を預かる重さで山登りが楽しめないこともあったそうですが、「メンバーが楽しめているのは自分がいるからだ」とリーダーの役割を捉えなおし、それをきっかけにリーダーとしての資質をもっと高めたくなったそうです。
・登山という、一度山に入ると自分の手では変えられない自然を相手に、与えられた環境下でいかにベストを尽くせるかを模索し、危機を克服すると達成感を得られ、逆境を楽しめるようになる、そして、チャレンジをする楽しさを知ると元に戻れなくなると浅野氏はまとめてくれました。
会員の方は、メニューより会員ログイン後に質疑応答と当日の資料をご覧いただくことが可能です。
続きは個人会員 / 協賛会員 / 組織会員 / AWP研究科同窓会組織のみ、閲覧可能です。
会員ログイン