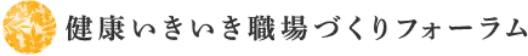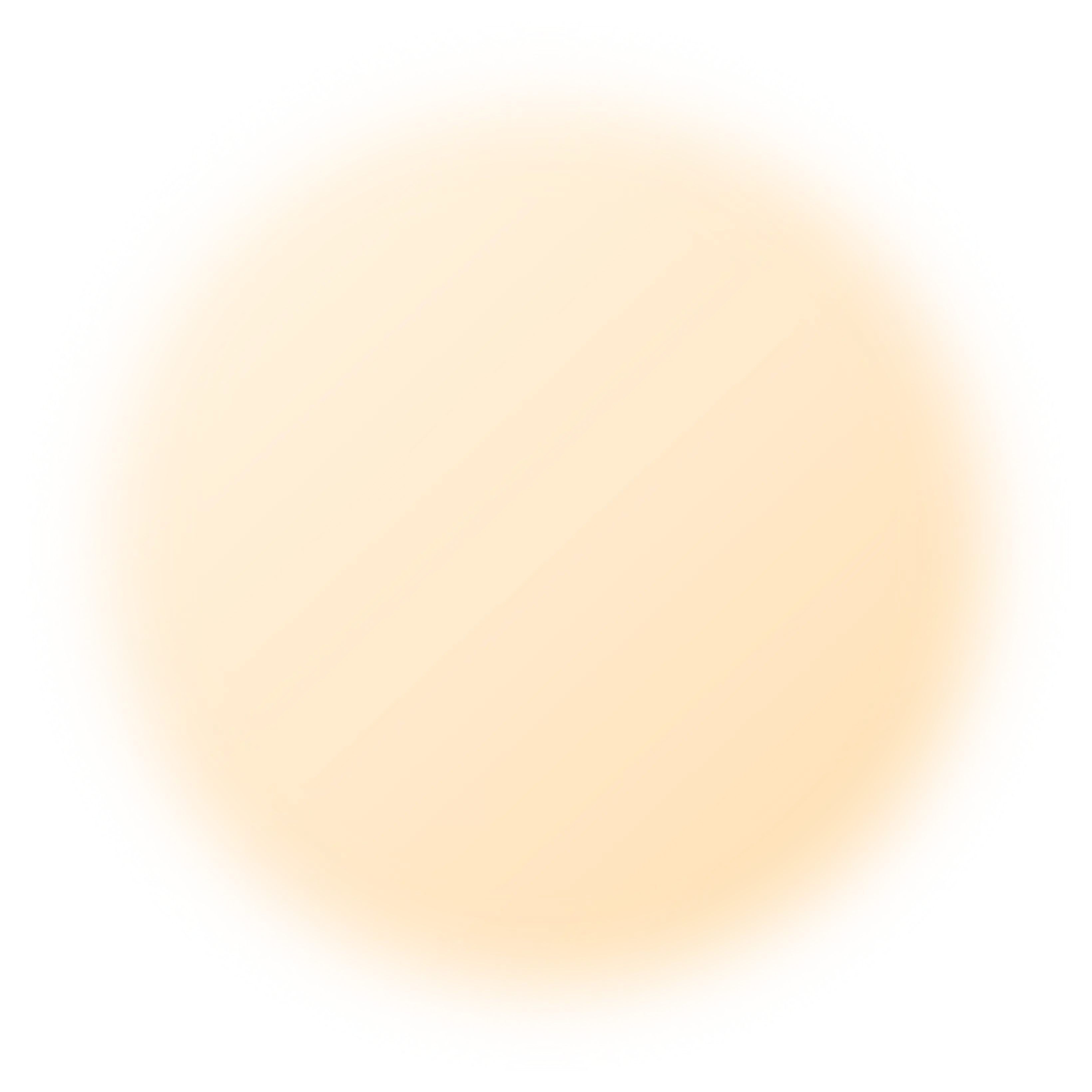去る6月16日、東京大学(東京・本郷)にて、健康いきいき職場づくりフォーラム定例セミナー「健康いきいき職場認証制度」を開催し、多数のご来場をいただきました。
当日は、事務局から、セミナー後(6月20日)にプレスリリースされた「健康いきいき職場スターター認証」の概要説明、プレ認証を申請した西日本旅客鉄道株式会社の事例紹介、認証制度検討のワーキンググループメンバーによるディスカッションが行われ、スターター認証の概要、意義、認証の検討過程での問題意識や期待すること、今後の展望などについて、多様な議論が行われました。
健康いきいき職場スターター認証とは?
まず最初に、健康いきいき職場づくりフォーラム事務局の中村より、今回公開される健康いきいき職場スターター認証の概要についての説明が行われました。本認証制度は、組織における健康いきいき職場づくりを推進する一つの基準を示すものとして、一般的にどのような取組によって健康いきいき職場が実現される可能性が高いかを示すとされています。また、その目的としては、①現在健康いきいき職場づくりを推進している組織の取組状況を評価する、②これから推進しようとする組織に対しどのように取り組めば効果的かを示す基準となることを掲げています。
評価基準として、以下5点があります。
①組織トップによる宣言(組織トップが健康いきいき職場づくりを積極的に推進することを表明、具体的な支援を宣言する)
②組織目標との連関(健康いきいき職場づくりが組織目標の達成に資するものであること)
③PDCAサイクルでの実践(健康いきいき職場づくりが組織内でPDCAサイクルに乗せて推進されていること)
④具体的な取組内容(健康いきいき職場づくりのための具体的な取組内容があること)
⑤定量的・定期的な評価の実施(「いきいき施策」=「仕事の資源」を増やすための施策の記載)
申請ステップは、申請書類の作成・提出(毎年4~8月)⇒事務局による面接(毎年6~8月)⇒認証委員会による評価(毎年9月)⇒評価結果フィードバック(毎年11月)⇒認証式(毎年12月)という流れです。また、対象は組織全体だけではなく、事業場、職場などより小規模なものも含んでいます。そして最後に、次年度に向けてより上位ランクの認証基準も開発予定であることも併せて紹介されました。
「ポジティブメンタルヘルス」の職場での展開と認証
続いて、認証制度の「プレ認証」に申請をされた企業の事例として、西日本旅客鉄道株式会社 健康増進センター担当課長の松永義高氏より、「健康いきいき職場づくりの取り組み~ポジティブメンタルヘルス・職場環境改善の展開」と題して講演いただきました。この中で、同社では、健康管理センターの取り組みとして、職場環境全体への働きかけ(ポピュレーションアプローチ)を行い、安全性やCS向上に向け、個々人の健康増進を図るとともに、働きがいと誇りを持てる職場~「あなたの元気でいきいき職場」~作りの支援を行い、企業理念の具現化に向け「考動」できるようすることを活動の基盤としていることが紹介されました。
また、同社は認証への申請メリットとして、「取り組みの社内での位置付けの明確化・体系化の促進」、「認知度の向上」「人事部門など他部門との連携促進」などがあるとしています。特に、連携については、人事主体の労働安全衛生方針と健康管理センター主体の健康管理方針のすり合わせが進み、年度基本方針にもその旨が盛られるようになりました。また、その過程で、ストレスチェックの実施、保健師による保健指導などを実施するとともに、職場環境改善(現在では「健康いきいき職場づくり」と社内でも提示)についても、「ぐっジョブカード」の利用や啓発ポスターなどの展開、保健師をファシリテーターとした健康いきいき職場づくりワークショップを通じた取り組みが計画・実行されているそうです。
一方で、一見同じような取り組みを実施する他企画部門との重複感による、参加する現場側の負担感、警戒感、温度差の存在や、活動時間と勤務体系の問題など、克服すべき課題も多いということもお話しいただきました。
東京大学大学院医学系研究科の川上憲人氏からは、経営メッセージとの連携、職場環境改善=「健康いきいき」という言葉がすでに利用されている点、産業保健スタッフの積極的な関与、「ぐっジョブカード」やフロアレイアウトの変更など様々な形で従業員参加型職場の環境の配慮がなされている点、調査結果を使いながらPDCAサイクルを回そうとしている点が有効だと指摘いただきました。一方、いかにして健康部門だけではなく、現場の管理者層や、人事・CSなど他部門も含めて経営として取り組むか、従業員参加型の風土を根付かせるかなど、さらに改善の余地があるのではないかというコメントがありました。
また、質疑応答を通じ、労組との連携、評価指標の全社的な明確化、現場へのフィードバック方法などを実体化させるかも重要ということが明らかになりました。
認証制度制定への経緯、問題意識を巡るディスカッション
次に、本認証制度の制定にあたり、制度の理念や内容、枠組みなどを検討したワーキンググループメンバーより、株式会社富士通 健康推進本部の玉山美紀子氏、大日本印刷株式会社 労務部エキスパートの稲原聡実氏、アステラス労働組合 中央執行委員長の橋本武士氏が登壇し、東京大学大学院の川上憲人氏とのディスカッションを行いました。その中で、玉山氏は、健康あっての仕事、職場という問題意識を持っており、いきいき職場のために何から始め、どういう姿勢が求められるのかという基準を作ることで、取り組みやすくなってほしい、という思いがあったとコメントしました。続いて、稲原氏は、自社のハードワークになりがちな職場風土に触れつつ、逆に健康な人がほったらかしということに問題意識を持ち、「健康いきいき職場づくりサポートプログラム」をはじめ、各種取り組みを開始していること、また、申請組織には、申請書類を書くなかで「ありたい姿」「どんな組織にしたいのか」などを考えるきっかけにしてほしい、とお話しになりました。橋本氏は、労働組合の立場としては、メンタルヘルスや健康だけでは取り組みに限界があるため、各社の持つありたい健康いきいき職場のイメージ、特にトップメッセージが大切になるとお話がなりました。ただ、その取り組みには時間がかかるので、まずは課題を共有し、取り組むきっかけにしてもらう意味で、あえて「スターター」にしたとコメントされました。
また質疑応答の際には、部署単位や職場単位でも申請を上げられるようにしたことについて、まずは志があるところから手を上げてもらうという意味がある点、大企業では同じ会社でも職種が違うと別会社のような場合も多いため、実際に機能する単位がいいという点が明らかになりました。また、PDCAサイクルの回し方のイメージについては、活動の中で各組織の取り組みは、それぞれの組織の自由度を持たせつつ、客観的な評価によって取り組みをブラッシュアップしていくことが重要とコメントがありました。また、「日本経営品質賞」など他のスキームとの連携、既存の健康管理施策(二次・三次予防)との棲み分けとして、既存施策を実施するのは大前提として、健康な人により積極的な投資分配をすることを意識して本認証制度を検討してきたことにも合わせて言及されました。
組織目標の連動が認証基準になっている点について、経営者や管理者が二の足を踏むのではないか、という質問に関しても、だからこそ、トップとの連携を図るための仕掛けを各組織で図る必要があり、そのための知恵を、認証を通じて共有できるようにしたい、という言及もなされました。