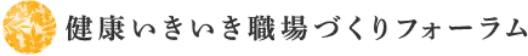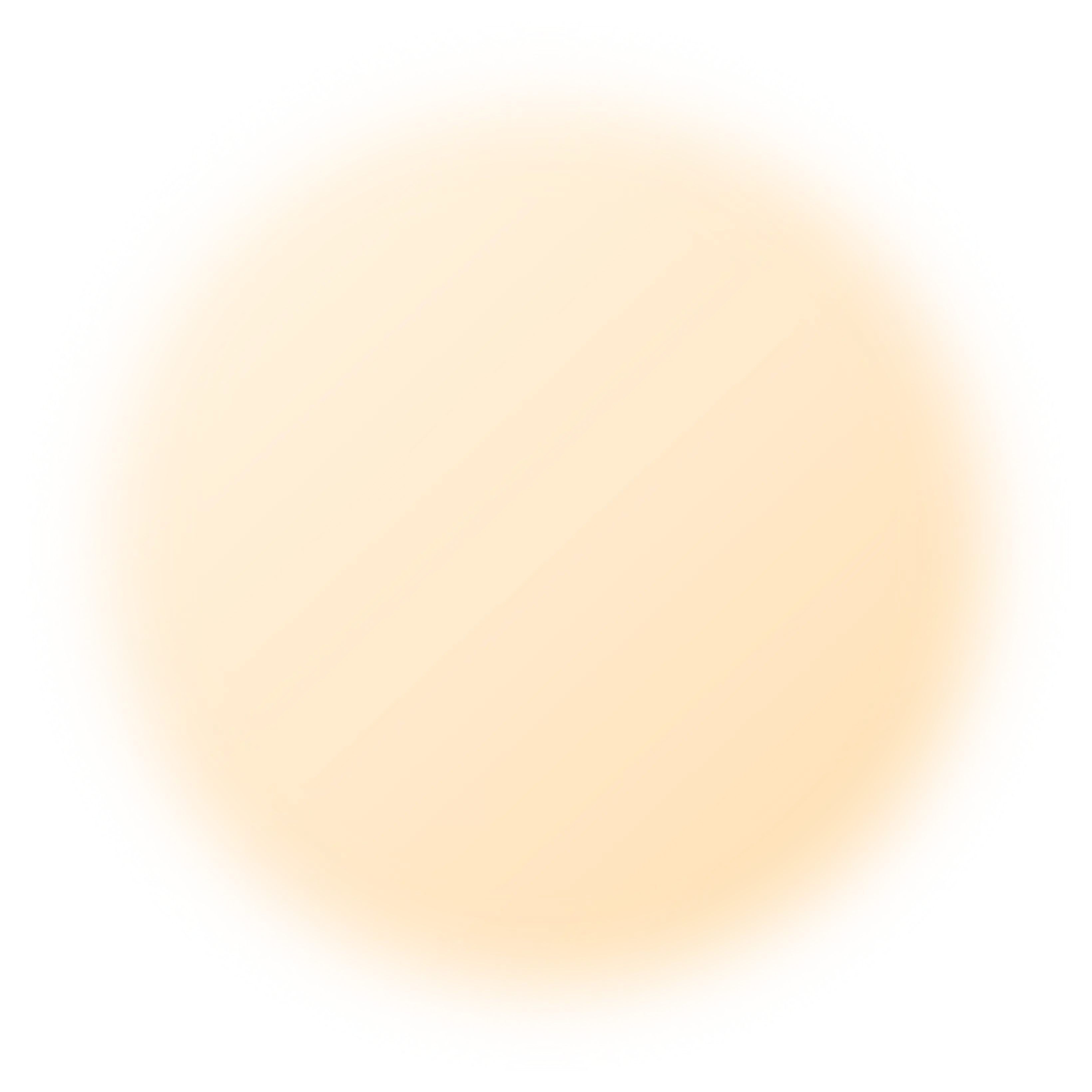去る4月23日、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンターにて、健康いきいき職場づくりフォーラム定例セミナー「労使で取り組む健康いきいき職場づくり」が開催されました。当日は、本フォーラムの発起人である島津明人氏(東京大学大学院准教授)とともに、旭化成労使、アステラス労使と4名の豪華ゲストにご登壇いただき、充実した内容となりました。
本編トップバッターには旭化成労組中央執行委員長の尾形清彦氏にご登壇いただき、「旭化成労組は、なぜ、健康いきいき職場づくりに取り組むのか」というテーマでお話いただきました。尾形氏からは、活動の具体論の前に、「なぜ取り組むのか」について、日本経済を背景とした組合と会社の歴史とビジョンを追いながらわかりやすくお伝えいただきました。
続く、旭化成株式会社上席執行役員の和田慶宏氏からは、メンタルヘルスについての旭化成グループの取り組みを、社員の意識調査のデータなどを交え具体的にお話いただきました。旭化成では、JMI健康調査(日本生産性本部 メンタル・ヘルス研究所)を活動の基盤にして展開していただいていました。当初はメンタルヘルス対策として始まりましたが、次第に職場活性化の取り組みとなってきたそうです。
アステラスの労使からは、まず労働組合中央執行委員長の橋本武士氏より、職場のメンタルヘルスを中心にした様々な労使協議体の取り組みについてご紹介いただきました。中でも、メンタルヘルス分科会では、「4つのケア+One」として、メンタルヘルスを単にリスクマネジメントにとどめず、そこにもうひとつ「快適職場づくり」を加え(+One)、継続的に活動しています。
最後に、アステラス製薬株式会社 人事部制度企画グループ部長の中島竜介氏より、メンタルヘルスに対する労使での取り組みと、会社での取り組みについてお話しいただきました。中島氏は特に、マネジャー教育が重要であると位置づけています。なぜなら、業績に対して組織風土は3割程度の影響があり、組織風土に対するマネジャーの影響は7割程度と高いからです。マネジャーが組織風土をよくしていくことが、業績向上につながる、ということを、繰り返し伝えて行くことが重要とお話いただきました。
二つの労使の方々から学ぶことは大変多くありましたが、共通するのは、大きく2点ありました。1点目は、労使が対立して主張しあうのではなく、ビジョンを同じにして情報共有しながら、まさに協調して活動を展開していること。2点目は、メンタルヘルスの取り組みを2次、3次予防にとどめるのではなく、1次予防を重視して展開していること、その中では、個人よりもむしろ、職場単位の「活性化」を重視していること、が挙げられます。
本セミナーは、労使関係という、健康いきいき職場づくりでは重要な「資源」となるものを、もう一度見直してみる良い機会となったのではないでしょうか。
会員の方は、メニューより会員ログイン後に詳細と当日の資料をご覧いただくことが可能です。
続きは個人会員 / 協賛会員 / 組織会員 / AWP研究科同窓会組織のみ、閲覧可能です。
会員ログイン