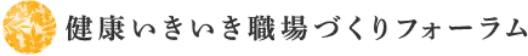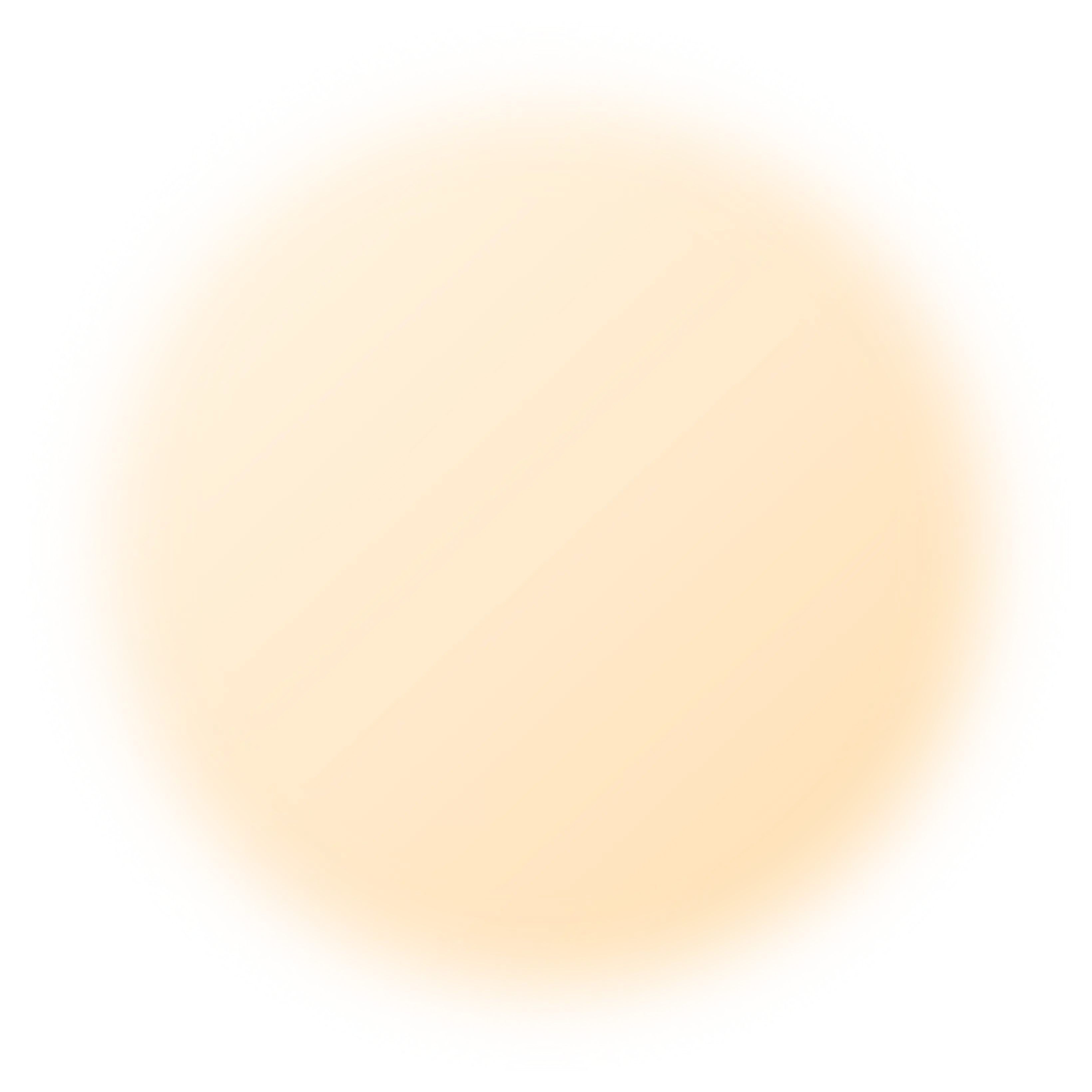5月30日、第2期Active Work Place研究会がスタートしました。
今期は4社8名の方がご参加くださいました。皆さん、フォーラム活動に積極的にご参加いただいている企業の方々で、今後の実践がとても楽しみです。
第1回は総論講義として、東京大学の川上憲人先生、一橋大学の守島基博先生よりご講義を、また、今後研究会に毎回参加してくださる、東京大学の島津明人先生もお越しいただきコメントをいただきました。また、参加者の皆さんには「事前課題」を基に自社紹介、自己紹介をいただきました。今回も人事部門、産業保健部門からのご参加があり、双方の側面から「健康いきいき職場づくり」をどのように進めるか、議論をしていきたいと思います。先生方の強力なバックアップの下に、またメンバーの皆さん相互の対話により、学び多い研究会となることと期待しています。
川上先生のご講義から興味深い解説がありました。それは、海外のメンタルヘルスをめぐる動向を見ていると、特にイギリスでは最近「ストレス」という言葉が出てこなくなってきている、ということです。代わりに、「Mental wellbeing」という言葉で表現されており、これを高める、という方針が打ち出されているそうです。メンタルヘルスの議論の方向性が、「ストレス」を、健康を害すものとして減らしていく、というアプローチから、もっとポジティブに、良いものを高める、という方向に移行しているのは、興味深いことです。「健康いきいき職場づくり」もメンタルヘルスというテーマでとらえたとき、まさに同じ方向を向いています。今後、日本だけでなく海外にも通じる取り組みとなる可能性が示唆されました。そのほか川上先生からは、健康いきいき職場づくりフォーラム立ち上げ以降の議論を踏まえ、健康いきいき職場づくりは新しいメンタルヘルス対策であると同時に、新しい経営戦略でもあることが伝えられ、より広い視点で考える必要があることが指摘されました。
守島先生からは、「健康な職場≒機能する職場」というキーワードの下、現在の日本企業で健康な職場が損なわれている実態がまず明らかにされました。これらは現場感覚として多くの方が持っている印象と同様でしょう。そこで必要な打ち手として「組織開発」という考え方があります。「組織開発」と一口に言っても様々なアプローチがありますが、いくつかの対応パターンの提示により、参加メンバーの組織では何が必要かを議論しました。
守島先生のご講義は毎回ゼミ形式で、インタラクティブに行われます。講義の時間を通じて、参加メンバーの皆さんがどのような状況下にあり、どのような問題意識をもっているのか、守島先生との対話の中で共有することができたのではないでしょうか。「組織開発」については、より具体的な方法として、第3回に大阪府立大学の北居明先生のセッションが待っています。組織開発を実体験していただき、頭だけでなく心で理解できる時間となるでしょう。
Active Work Place研究会第2回は、直後の6月9日-10日に合宿形式で行われます。ここでは第1期メンバーの最終回との合同開催により、より多くの実践事例に触れあうこととなります。ご期待ください。