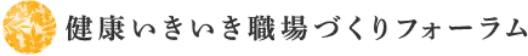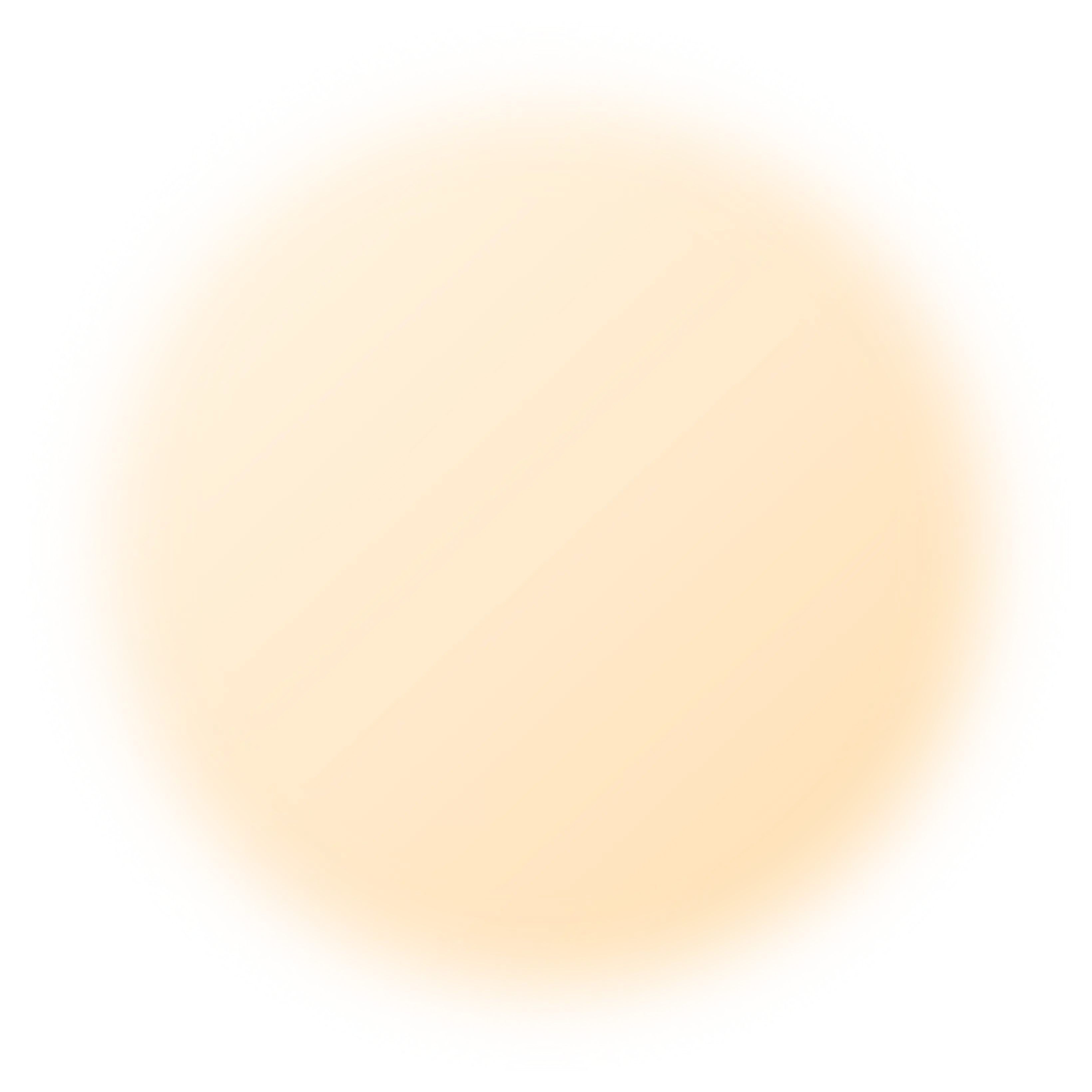去る8月25日に、第3期Active Work Place研究会の第2回を開催しました。本研究会は、約1年間7回にわたる会合を通じ、「健康いきいき職場づくり」の最新理論を学習いただくと同時に、「いきいき職場」実現への、各社での具体的な行動計画策定・その実践を行うことを目的にしております。今回は、島津明人氏(東京大学大学院准教授)・北居明氏(甲南大学教授)を迎え、「方法論の理解と実践」と題し、参加4組織の自組織の状況や目指したい姿について、アセスメント結果及びチェックリストから抽出し、活発な議論が行われました。また、従業員の参画を得る上で不可欠である組織開発の手法の学習と体験セッションが行われました。
「強みを伸ばす視点、弱みを、弱みとしてではなく、挑戦すべきチャレンジとして捉える視点が重要」(島津明人氏)
まず最初に、参加4組織より、前回課題の発表と意見交換、島津明人氏(東京大学大学院准教授)からのアドバイスが行われました。
(1)「いきいき職場資源チェックリスト」で、自職場にどのような資源があり、どこの資源を増やしていきたいのかの発表
(2)各種アセスメントから見えた自職場の現状
(1)では、
①方向性がメンバーで共有された職場
1 組織の目指すべき目標の共有
2 トップによるリーダーシップや対話
3 ミドルレベルでのリーダーシップの発揮
4 垣根を越えた各種対話・交流の促進
5 手続きの公正さ・声が反映される仕組み
②成長へのチャレンジが促進される職場
6 人財育成・各種研修の実施 7 成長機会やチャレンジの促進 8 キャリア開発の推進
③安心して働ける職場
9 WLB・ダイバーシティへの配慮
10 物理的な環境整備
11 コンプライアンスへの対応
12 健康増進施策
13 休暇取得・時間管理の徹底
④全員参加への仕掛けのある職場
14 福利厚生・各種イベント
15 各種表彰
16 アセスメントの活用
の観点から自職場がすでに持っている資源(及び具体的な取り組み=強み)、今後高めていきたい資源(=チャレンジ)を各組織より発表してもらいました。様々な規模・業種・特徴を持つ組織が集まる本研究会らしく、重点目標もそれぞれ。特に、「チャレンジ」については、すでに取り組みをしている組織からの助言を求める相互アドバイスが活発に行われました。
(2)については、ストレスチェックを活用している組織や、社員満足度調査、労働組合実施の調査を利用するケースなど、様々な活用法が示されました。そのなかでは、メンタルヘルスへの視点はもちろん、職場環境、そこで働く方々の満足度、仕事への意義づけ、施策の浸透度など、多くの要素が「資源」になりうることが改めて確認されました。
続いて、「アセスメントの活用について」と題して、事務局よりサーベイを活用するする際のポイントとして、「何のために測定するのか」「何を、どのように測定するのか」の観点からの説明が行われました。具体的には、①活動の見える化、②社内の説得のロジックへの活用がサーベイ活用の根本にあり、その際に、各フェーズで留意すべきことが案内されました。
「ポジティブな問いかけが、変化を成功させる。そこに着目したのがAIのポイント」(北居明氏)
続いて、従業員の参画を得る上で重要な組織開発の視点について、AI(Appreciative Inquiry)の手法を活用した方法論を、甲南大学教授の北居明氏よりレクチャーいただき、それを体験するセッションが行われました。
まず、組織開発についての案内と、その中でAIが属するポジションや特徴が示されました。組織開発は、「組織のパフォーマンスを上げ、組織目標を達成するために必要な組織を戦略的に作り上げる活動」と定義され、その方法論として、サーベイを活用した診断型と、メンバー間の関係性の向上をキーにした対話型があることが紹介されました。
AIの特徴としては、問題点の発掘より、「強み」を発見するアプローチで組織変革につなげるということが挙げられ、そのために
発見(Discovery)-自分たちが最も意欲的にさせるエピソードを探る
夢(Dream)-エピソードを基に、目指すべき将来像を描く
デザイン(Design)-将来像を基に、最も望ましい組織像を描く
運命(Destiny)-具体的アクションを決める
の「4Dサイクル」を経ることで、職場を活性化させる取り組みを取ることが要請されています。
後半では、体験セッションとして、ポジティブな形に「問い」を変える試みを実践すべく、「ポジティブ・インタビュー」=最高の瞬間の相互インタビュー、「ポジティブ・コアの共有」=グループ内でのエピソードの共有や相互表彰、「未来像の共有」=最高の未来像の共有とポストイットへの書き出し、理想の職場に向けてのストーリー化をグループに分かれて実際に行いました。
終了後、参加メンバーは長時間のセッションにもかかわらず、笑顔が絶えず、非常に「活性化」している様子がうかがえました。



次回第4回は、9月28日(月)に開催を予定しています。
が東京大学大学院教授の川上憲人先生より、「健康いきいき職場づくりとは」と題して、総論講義が行われました。その中で、川上氏は、健康いきいき職場づくりは、新しいメンタルヘルス対策としてだけではなく、新しい経営戦略として行われることが案内されました。その背景として、我が国のメンタルヘルス対策の変容(リスクマネジメントからポジティブへ)、理論的背景の変化(健康障害モデル=「負担を減らす」から「資源を増やす」へ、ワーク・エンゲイジメント、mental wellbeing、心理的資本、各単位での社会的・心理的資源の重要性など)、取り組み主体の変化(ヘルスセクターからノンヘルスセクター(ビジネスセクター=人事、経営企画、労組など)との連携)などがあるとのことです。