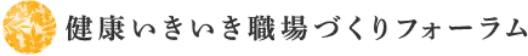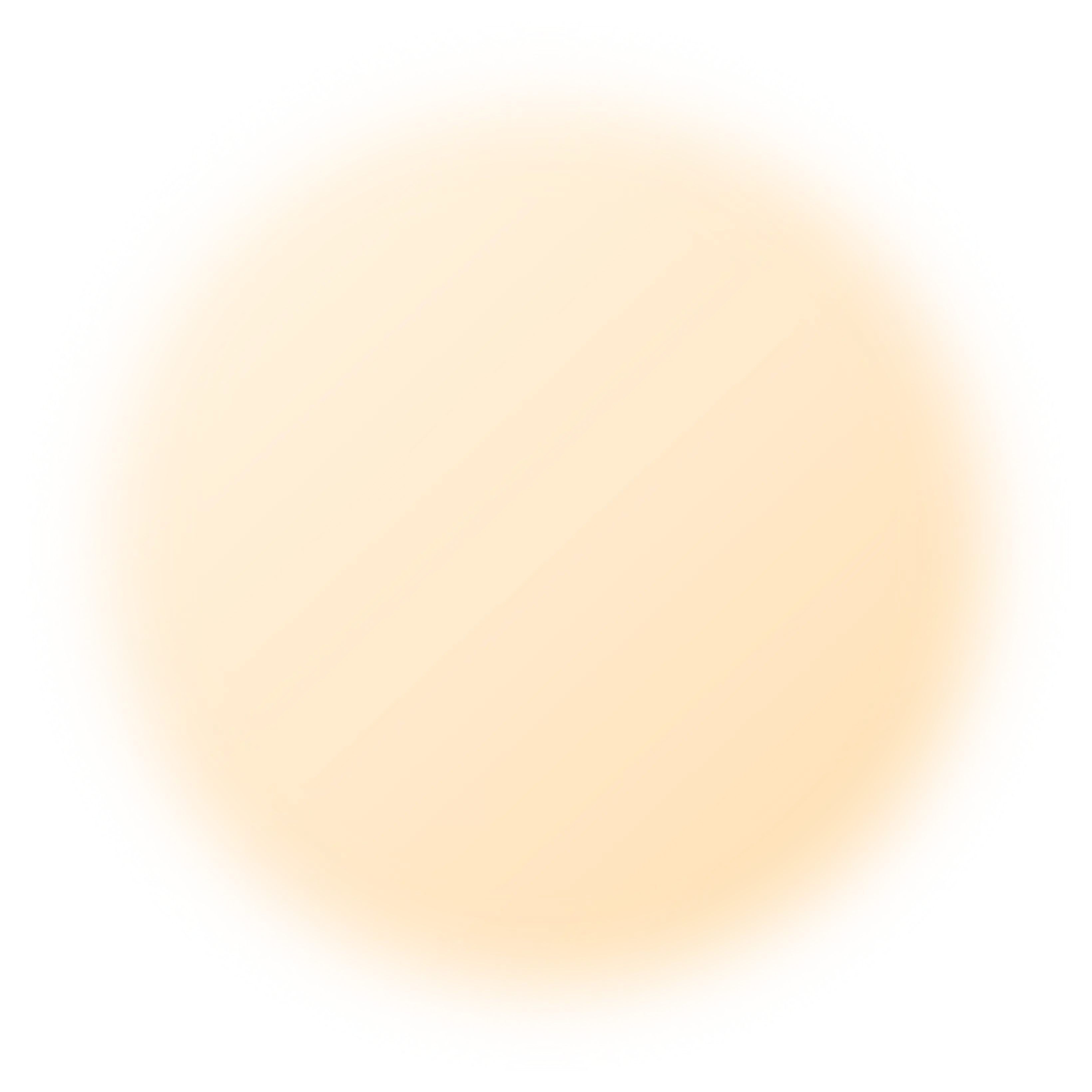去る9月28日に、第3期Active Work Place研究会の第4回を開催しました。本研究会は、約1年間7回にわたる会合を通じ、「健康いきいき職場づくり」の最新理論を学習いただくと同時に、「いきいき職場」実現への、各社での具体的な行動計画策定・その実践を行うことを目的にしております。今回は、島津明人氏(東京大学大学院准教授)・今村幸太郎氏(東京大学大学院特任助教)を迎え、「方法論の理解と実践」と題し、参加4組織のグッドプラクティスや、従業員の参画を得る方法論の一つである参加型ワークショップの実践法・体験セッションが行われました。
「Good Practiceをお互い持ち寄り、よいところを自組織でのいきいき職場づくりに取り込んでいってほしい」(島津明人氏)
まず最初に、参加4組織より、前回課題の発表と意見交換、島津明人氏(東京大学大学院准教授)からのアドバイスが行われました。
前回課題:「自組織内のGood Practice報告シート」
本課題に対し、各組織から多くのグッドプラクティスが寄せられ、それを巡って参加各社の質問、相互アドバイスが行われました。以下はその一例です。
(主なグッドプラクティス)
・「ほめほめ隊」-機密性の高い職場で、職場内・職場間のコミュニケーションを高めるため、メンバーが職場訪問をして、職場の強みや取り組みを褒め、それを社内で発信・共有する
・「工場長と語る会」-トップダウンとボトムアップの円滑化を図るべく、社員食堂の協力も得つつ、「語る会」を各職場で開催
・「フェスタ委員会」の活用-各事業所で役員をトップとし、若手社員を中心とした家族も含めた交流イベントを開催。好評の声がメンバーのモチベーション向上に寄与
・ストレスチェックの活用-ストレスチェックの結果を基に、所属長向けの分析結果説明、強み・弱みの検討会実施
・部署独自の運動会-各職場のレク委員を中心に大会を実施し、一体感を醸成。他部署への紹介・展開も視野に
・サークル活動紹介会-労組主催でサークル活動を紹介する会合を実施。単純な照会だけではなくバンドの生演奏などのサプライズも入れて、一体感の醸成へ
・ハロースマイル活動-朝夕の挨拶運動(朝スマ・夕スマ)によって、同僚・管理監督者とのコミュニケーション向上、定時退社によるWLB促進
・「こうのとりプロジェクト」-産前産後の出産・育児のフォローを経験者中心に行うことで、業務調整やメンバーへの権限移譲、ネガティブな離職を防止
・残業取得システム-恒常化したサービス残業を防止すべく、残業を申請し、ネームカードに残業時間を記し、見える化することにで意識向上。あわせて、評価制度も改訂し「残業をしない」ことを高評価へ

「従来型の職場環境改善と似て非なる部分があるのが健康いきいき職場づくりワークショップの特徴」(今村幸太郎氏)
続いて、従業員の参画を得る上で欠かすことのできない参加型ワークショップ以下の一つである「健康いきいき職場づくりワークショップ」(以下いきいきWS)について、東京大学大学院の今村幸太郎先生より説明いただき、実際に研究会メンバーがいきいきWSのファシリテーターになることも想定した体験セッションを行いました。
今村氏によると、従来型の職場改善活動といきいきWSの違いは、
・目的 従来型:いきいきWS=不調防止・ストレス要因の除去:一体感・主体性向上
・方法 従来型:いきいきWS=改善ポイントのリストアップ:さらに伸ばしたい点のリストアップ
・効果 従来型:いきいきWS=職場環境改善・心身健康増進:職場の各種資源向上・いきいき向上
といった点にあるといいます。また、ファシリテーターは、いきいきWS参加者に分かりやすく理論的背景などを説明できるためのスキルを身に着けておく必要があるとのことでした。そのためには、事前準備・実施・事後フォローの各過程、管理者への働きかけなどそれぞれで押さえるべきポイントがあるとのことで、WS当日だけではなく、サイクルの一環として位置付けることが受容であるとのことです。
このあと、実際に、架空の職場を題材に、いきいきWSの体験を行いました。参加メンバーはグループに分かれ、それぞれで、
「目標とする職場のあり方の確認」⇒「目標とする職場づくりのためにうまくいっている点」⇒「具体的に良い点とその理由」⇒「これから必要なこと、さらに伸ばしたい点」⇒「具体的対策のアイディア」
の順で議論を重ねました。

そののちに、それぞれのグループで考えたまとめシートを発表しました。同じ課題であっても、それぞれの着眼点があり、目指す職場像が見えてくるのがいきいきWSの特徴です。前回のAIの体験セッションもそうでしたが、澪乗り出すようにして時間を忘れてプランを行い、発表をする参加メンバーの姿が非常に印象的でした。
本研究会は、前半戦では理論と各職場の持ち味の抽出、改善のための具体的な方策を中心に学習してきましたが、次回からはいよいよ実践段階に入ります。次回11月16日(月)は、各職場の行動計画を発表頂く予定です。