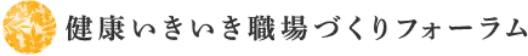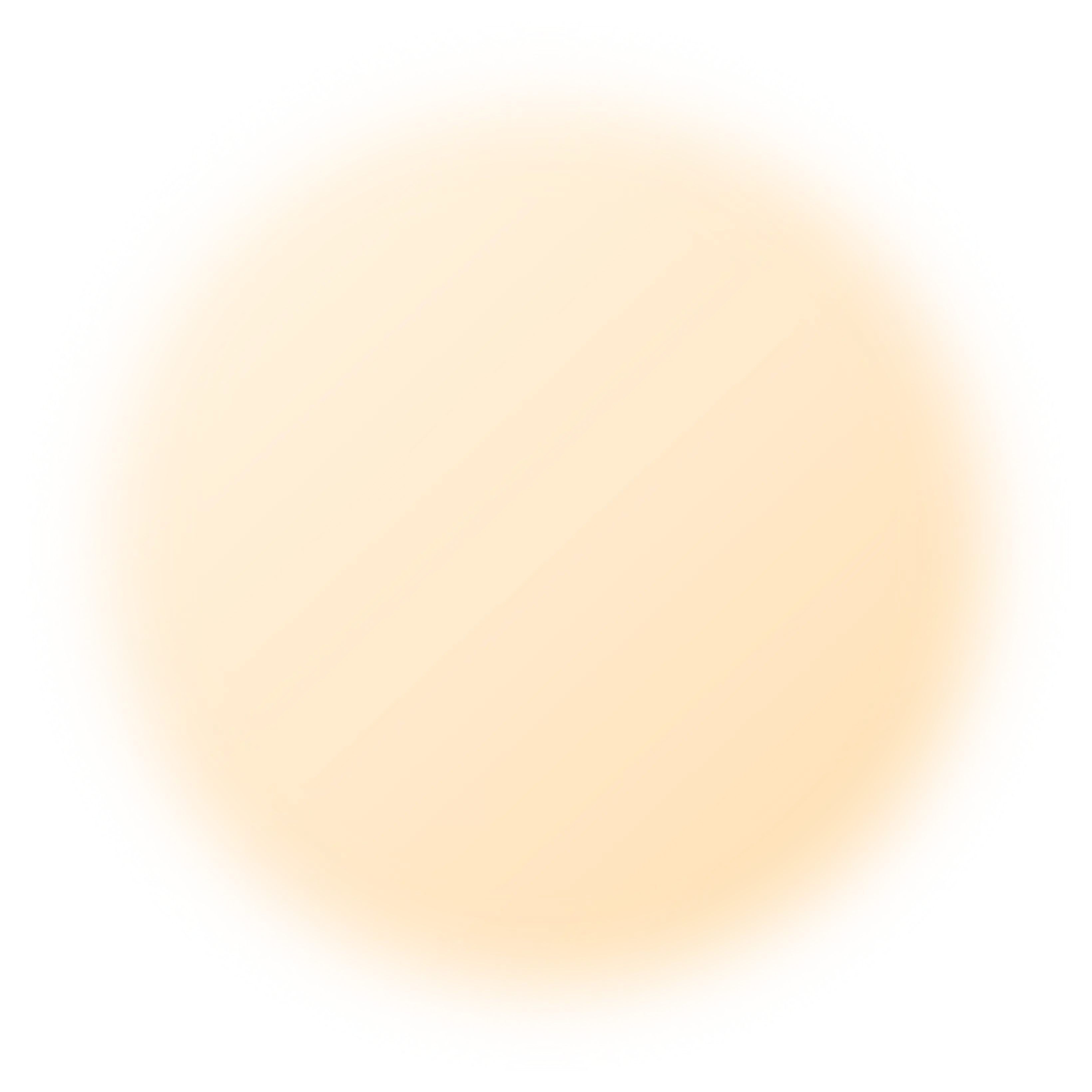定例セミナー「職場再生 ~ソーシャル・キャピタル論に注目して~」開催!
去る10月7日、東京大学医学部会議室にて、健康いきいき職場づくりフォーラム定例セミナー「職場再生 ~ソーシャル・キャピタル論に注目して~」を開催し、多数のご来場をいただきました。当日は、川上憲人先生(東京大学大学院教授)より「健康いきいき職場づくりと職場の資源アップ」と題してご講演をいただいた後、西村孝史先生(首都大学東京大学院社会科学研究科准教授)と、江口尚先生(北里大学医学部助教)より、経営学と医学のそれぞれのお立場から、ソーシャル・キャピタルとは何か、についてご講義いただきました。セミナー後半は毎回と同様、川上先生、西村先生、江口先生にご登壇いただき、今職場で起きていることと、ソーシャル・キャピタルの関係について、現実的な視点からの議論が交わされました。
また今回はプログラム途中、西村先生の講義の後、オブザーバー参加をいただいていた守島基博先生(一橋大学大学院教授)より、健康いきいき職場づくりにおけるソーシャル・キャピタルは何か、についてコメントをいただきました。「ソーシャル・キャピタル」とは概念が広いため、人によってイメージするものが違うかもしれません。健康いきいき職場づくりとして注目すべきは、単に人と人のつながりだけを見るソーシャル・キャピタルだけではなく、会社への信頼や安心感、公平な扱いといった、人的ネットワークに依存しない資源の方が重要であるとのご指摘をいただきました。
「職場の社会的心理的資源の一つとしてのソーシャル・キャピタル」
冒頭、川上先生より健康いきいき職場づくりの理論について講義をいだき、健康いきいき職場づくりの視点の一つである「職場の社会的心理的資源に注目する」観点から、ソーシャル・キャピタルの重要性が語られました。
職場のメンタルヘルスにおいては、従来型の対策として「仕事の量的質的負担を減らす」ことが大切と考えられていますが、負担を減らしてもいきいきは上がらない、ということがわかっています。川上先生の現場感からも、健康管理を頑張ってもうつ病がなくならないと感じているそうです。何が根本の問題かというと、組織の経営方針や人事評価制度など、健康以外の要因からの影響が大きいのです。また、コミュニケーションの問題からは、例えば精神障害の労働災害認定の動向みると、職場のいじめやいやがらせなどを原因とする事例も増えています。川上先生からはこれらを踏まえ、健康管理の視点からだけでなく、職場の社会的心理的資源(=仕事の資源)を増やしていく活動として、ノンヘルスセクター(健康管理以外の領域)からのアプローチが重要であると解説されました。そして、その具体的方法として、会社・事業場レベル、部署レベル、個人レベルにそれぞれ対策方法があり、事例として株式会社デンソーの社長直轄プロジェクト、英国HSEマネジメントコンピテンシーを使った管理職教育、また健康いきいき職場づくりを目指した参加型職場環境改善のワークショップが紹介されました。
「ソーシャル・キャピタル論概観と人材マネジメントとの関係」
続いて、まずは経営学の視点からのソーシャル・キャピタル論として、西村孝史先生(首都大学東京大学院社会科学研究科准教授)より「ソーシャル・キャピタルと人材マネジメント」と題して講演いただきました。西村先生は経営学の中でも人材マネジメントがご専門で、川上先生のいうノンヘルスセクターからのお話となりました。西村先生からは、ソーシャル・キャピタルとは何か、また人材マネジメントの変化を背景に、これをどう組織に活かせるのか、という視点からお話をいただきました。
ソーシャル・キャピタルには様々な定義があり、カバーする範囲が大変広い概念です。西村先生からは、「『人脈』『つながり』あるいは『絆』から得られる『資源』」という紹介がされました。細かく見ると、「人脈」、「つながり」、「絆」はソーシャル・ネットワーク、その結果としての「資源」がソーシャル・キャピタルと言え、どのようにくくるかは研究者の中でも分かれるようです。
なぜ、今ソーシャル・キャピタルへの注目が集まっているのかというと、西村先生によれば「失われた20年」において、企業は「働く個人に負担をかけた」(成果主義、キャリアの自己責任、非正規労働拡大等)といえ、今その反動として、組織への視点(組織の強みへの再考)に動いているのではないかという見方があるとのことです。また、ソーシャル・キャピタルは組織や個人が状況に「埋め込まれた」結果としての資源であるため、他社が容易に真似できない組織能力である、ということも注目される理由の一つです。
ソーシャル・キャピタルを規定する要因としては、個人の属性、職務設計や上司との関わり、そして人材マネジメントという3つの側面があります。その中でも、人材マネジメントの諸機能をどう活用できるかをご指摘いただきました。例えば、ごく当たり前の話だが、長期雇用が維持されていると、ソーシャル・キャピタルが出来やすいということが研究でわかっている。また、ソーシャル・キャピタルが職場で形成されるのは、担当から係長に上がっているときです。つまり、この時点で本人をどういう状況に組み込むかを考えることは、その本人にとって決定的な影響があります。また、組織としてはソーシャル・キャピタルに配慮した人事異動を行うことで、単純に玉突きのような異動に比べ、より意味のあるものになる、ということが言えるそうです。
最後に、西村先生からは、人事、人材マネジメント、あるいは労組の方々はある程度、働く人々のつながりを作ることが操作可能であることを認識して、それをうまく活用してほしい、というメッセージが伝えられました。
「ソーシャル・キャピタル⇔労働者の健康⇔組織の業績」
次に、医学の視点から、江口尚先生(北里大学医学部助教)より「職場のソーシャル・キャピタルと健康影響」というタイトルでご講演をいただきました。江口先生は医学博士、産業医として外資系企業、日系企業にお勤めの後、経営学修士(MBA)も取得されるというご経歴の持ち主です。医学の視点からのソーシャル・キャピタルという意味での定義は、「相互扶助」「互恵性の規範」「信頼」から構成され、様々な方法を通じて個人の健康影響を与えるもの(Ichiro Kawachi)との紹介がありました。
江口先生による、現在の職場の状況のご認識も西村先生と同じく、人間関係(つながり)が弱くなっているというものでした。実際にデータを見ても、職場の人とのつながりは「形式的」「部分的」付き合いが増え、「全面的」付き合いは減っていたり、労働者の強い不安の原因は職場の人間関係が一番多かったりという事実があります。これら、ソーシャル・キャピタルの減少と言われる事象と、健康はどのような影響があるかということをみると、やはり相関関係があることがわかっています。また、江口先生の研究によると、ソーシャル・キャピタルが高まると、健康度が上がる、という因果関係も明らかになっているそうです。
そこで、ソーシャル・キャピタルを高めるために何ができるかについて示唆をいただきました。重要なポイントはコミュニケーションにある、というのが江口先生のご指摘です。ただ、このとき注意しなければならないのは、これまでの日本の職場環境のように「暗黙」が通用し、それを前提にしたコミュニケーションを考えてはいけないということです。これまでは、男性、正社員、日本人、という構成がメインでしたが、今それは大きく変わっています。以前は朝の挨拶などしなくても関係に影響はなかったかもしれませんが、今は意識して挨拶をきちんとするなどしないと、相手には伝わりません。こうしたコミュニケーション上の配慮のなさが、現在は結果としてのハラスメント問題などにも発展しているのです。江口先生によると、現在は安全配慮義務からさらに進んで、「職場環境配慮義務」が求められるようになっているそうです。
こうした現状の上で、コミュニケーションを円滑にし、ソーシャル・キャピタルを増やすために、江口先生は経営理念の活用を提案されています。多様な人材が働き、暗黙の前提が崩れている現在の組織においては、意識的に共通目標としての経営理念を掲げ、社員に伝え、また社員の組織への信頼を構築する必要があります。
会員の方は、メニューより会員ログイン後に質疑応答と当日の資料をご覧いただくことが可能です。
続きは個人会員 / 協賛会員 / 組織会員 / AWP研究科同窓会組織のみ、閲覧可能です。
会員ログイン