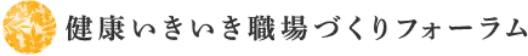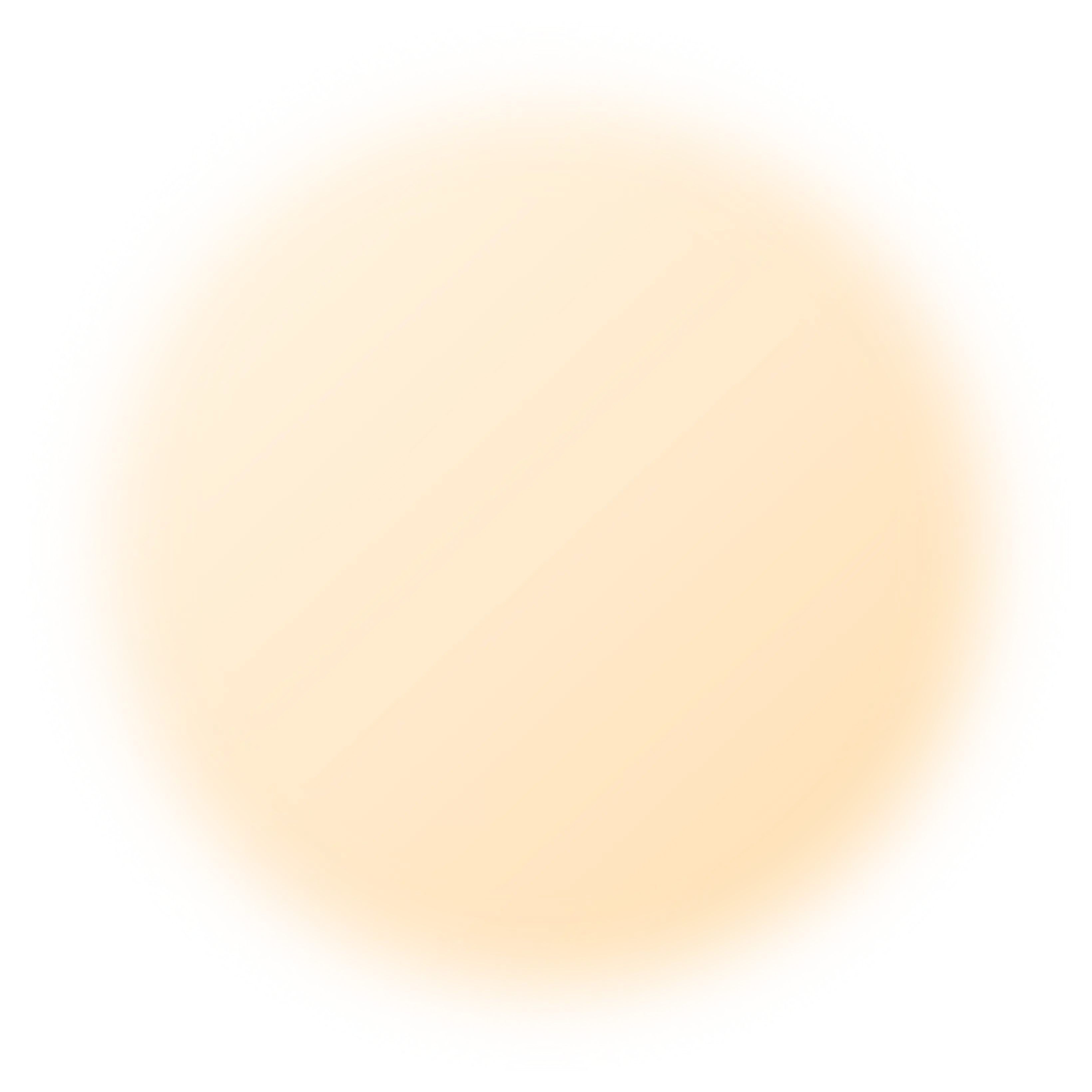定例セミナー「健康いきいき職場づくりアセスメント」開催!
去る8月5日、東京大学医学部会議室にて、健康いきいき職場づくりフォーラム定例セミナー「健康いきいき職場づくりアセスメント」を開催し、多数のご来場をいただきました。当日は、川上憲人先生(東京大学大学院教授)より「健康いきいき職場づくりにおけるアセスメントの活用」と題してご講演をいただいた後、佐藤光弘氏(富士通株式会社健康推進本部健康事業推進統括部長)と、根本忠一(公益財団法人日本生産性本部メンタル・ヘルス研究所研究主幹)より、アセスメントを活用した取り組み事例を発表いただきました。最後に質疑応答もかねてのパネルディスカッションにより、話題はアセスメントの活用から、それを用いた職場改善の必要性、また経営者の理解が欠かせないことなど、健康いきいき職場づくりを進める上での根本的な課題や方向性について議論がなされました。
「アセスメントを活用してPDCAサイクルを回すことが重要」
冒頭、川上先生よりアセスメントの活用がなぜ健康いきいき職場づくりに必要なのかについて、この取り組みをPDCAサイクルに載せて回すことができ、これが重要であるためであることが伝えられ、以下のようなコメントをいただきました。
昨今、国際動向においても、職場のメンタルヘルスの活動においても他の業務と同様に、PDCAサイクルによって、計画立案し、実施し、その結果を評価・見直しすることが推奨されています。同様に、健康いきいき職場づくりにおいても、まずは自社や自組織の健康いきいき資源を評価するところからスタートすることが効果的です。健康いきいき職場づくりにおいて具体的なアセスメントツールを特定してはいませんが、以下4点を満たしているものであることが好ましいと言えます。
① 従業員の「いきいき」、職場の一体感、心身の健康についての質問項目が含まれていること
② 職場組織の心理社会的資源についての質問項目が含まれていること
③ 「標準」集団と比較できること
④ 繰り返し測定できる方法であること
また、アセスメントはそれを実施しただけでは意味がなく、これを基に自分の職場の人と組織の特徴を理解し、対策ポイントを見つけること、またその対策の効果を知るために活用することが重要であると伝えられました。
「経営者には15分でわかる資料でフィードバック」ストレス診断×ES調査をビジュアルでアピール
続いて事例発表の1つ目として、富士通株式会社健康推進本部健康事業推進統括部長の佐藤氏より、ご発表いただきました。富士通株式会社では、健康推進本部として「社員のみならずその家族を含めた健康の保持増進に取り組む」ということが目標に掲げられています。そのために、社員のヘルスリテラシー(自らの健康をケアする能力)を高め、安心して幸せに働ける風土構築を目指しています。その方針に沿って同社では、「職業性簡易調査票を用いて全社員対象のストレス診断を実施し、これを活用してセルフケアや相談対応につなげています。同社の取り組みに学ぶべきところは、こうした調査結果をきちんと経営層に説明するため、「忙しい経営者が15分で理解できる」内容になるよう、ビジュアルでわかりやすく表現し、資料の分量も、A3版1枚にまとめているということです。こうしたわかりやすい資料により、経営層や本部長クラスからの理解や支援を得ています。一方で、これを単なるストレス診断で終わらせず、別に実施しているES(従業員満足度)調査と連動した分析を開始しました。これにより、ストレス診断結果とES調査との間に有意な相関があることがわかりました。ES調査の目的は同社の企業指針(価値観)や行動指針の浸透を図るものであるため、これとストレス診断結果との相関が高いことは、今後の改善施策を打つ上でも重要な情報となります。
今後、同社の取り組みは健康管理部門によるリスク対策という側面からだけでなく、よりポジティブなメンタルヘルスを目指して、組織の活性化と結びつける活動に移行していきます。
同社の取り組みからは、ストレス調査の結果をわかりやすく伝えること、またストレス調査としてだけでなく、ワーク・エンゲイジメントや組織活性化に結び付けて分析し、有効な施策を打ち出していくことの重要性が伝えられました。
「職場単位の組織活性化の推進」経営の健康度を図り、改善する指標として活用
事例発表の2つ目として、公益財団法人日本生産性本部メンタル・ヘルス研究所研修主幹である根本より、発表がありました。同研究所では、WHOによる健康の定義※に基づき、1970年代より、「JMI健康調査(心の健康診断)」の開発と普及を行って来ました。研究所では、メンタルヘルスの三規準を制定し、「自分の可能性を十分に発揮していること」など、ポジティブな状態を「メンタルヘルス」と位置づけて来ました。その意味で、JMI健康調査は本来ストレス診断という枠組みではなく、人的資源の効果的な活用のために実施されて来ました。根本からは、こうした前提を踏まえたうえで、JMI健康診断の結果による組織分析に基づいた、管理職教育や職場活性化の具体的事例と、さらにその施策を踏まえた調査結果の変化について発表がありました。なお組織分析結果については、単に結果のフィードバックに留まらず、それを活かして「改善をデザインすること」に注力していることが伝えられました。発表された二つの改善事例のうち、一つは、JMI健康調査の実施と、それを基に実施された「JMIプロジェクト会議」により、実際に「職場が変わった」と実感する社員の方のインタビューがビデオで上映されました。また、もう一つの事例は、経営の仕組みを変える改善手法ではなく、それを機能させる社員のモチベーションアップに注目し、特に管理者の資質の底上げを図る研修実績が発表されました。いずれのケースも、Before/Afterで調査結果に明らかな改善が見られ、この取り組みが効果的であったことが説明されました。
この発表からは、メンタルヘルス対策は組織の経営ビジョンをベースにした人づくり(人材育成)ビジョンを実現するためにあるということ、またその調査(アセスメント)は、正確な実態把握に基づく現場(職場)自らの改善にとって必要であることが伝えられました。
※WHO憲章
健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、全てが満たされた状態にあることをいいます(日本WHO協会)
会員の方は、メニューより会員ログイン後に質疑応答と当日の資料をご覧いただくことが可能です。
続きは個人会員 / 協賛会員 / 組織会員 / AWP研究科同窓会組織のみ、閲覧可能です。
会員ログイン