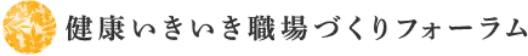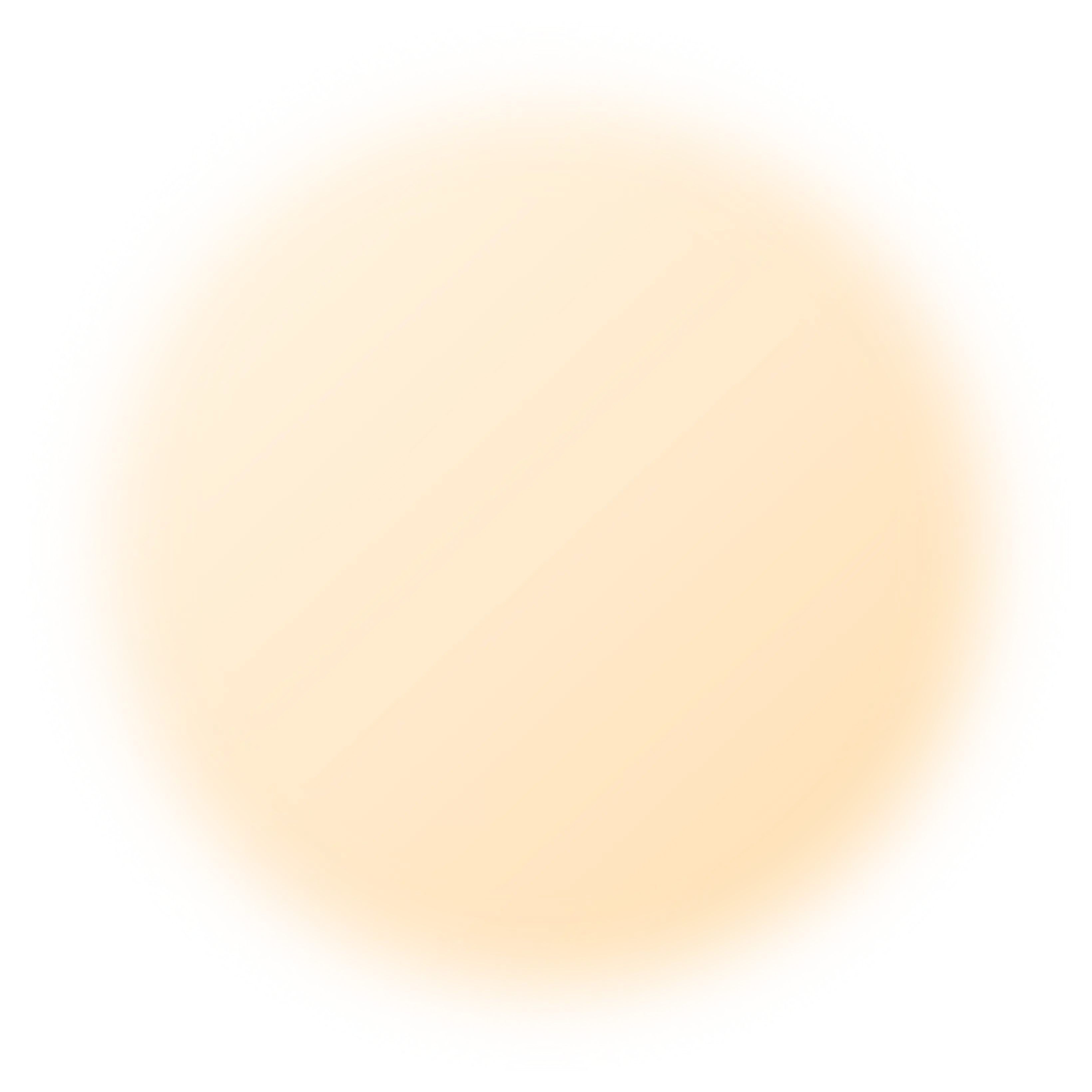去る2015年10月19日、健康いきいき職場づくりフォーラム定例セミナー「健康いきいき職場最新理論~研究者ブログ出版記念~」が開催され、多くの方にご参加いただきました。この日は、当フォーラムHPに月一回連載形式で掲載している研究者ブログが、『職場のポジティブメンタルヘルス』として出版されたことを記念し、執筆者の方々招いて開催しました。また、企業現場及び学際の立場からのコメントや、会員限定での懇親会ワークショップも盛り込んだ、「理論と実践の融合」を考える会となりました。
「実務家が理論を学ぶ意味とは?」(島津明人氏)
まず最初に、中心執筆者である島津明人氏(東京大学大学院医学系研究科准教授)より、「職場のポジティブメンタルヘルス~理論を学ぶ意味~」と題してお話しいただきました。そこでは、書籍の概要~「ポジティブなメンタルヘルスを推進するための考え方(理論)と進め方(実践)を意識した書籍であること~や、内容として、「職場のポジティブメンタルヘルス」を起点に、「組織マネジメント」「セルフマネジメント」「生活のマネジメント」についての最新理論が掲載されていることが紹介されました。また、島津氏は、理論を学ぶことの意義として、
1-様々な立場の方との共通言語を持つことで、活動を推進しやすくなる
2-現場の活動に裏付けを持って計画・立案・実施できる
3-活動の一般化・横展開が可能になる
ことがあるとして、ぜひそういった観点で本日のセミナーを活用してほしいと呼びかけられました。
「『感謝』のポジティブ・スパイラルに向けて」(大塚泰正氏)
続いて、組織マネジメントへの視点として、大塚泰正氏(筑波大学人間系心理学域准教授)より、「『ありがとう』の一言がみんなを幸せにする~感謝すること、感謝されること~」と題し、「感謝」を起点に自身の、周囲のいきいきが高まる仕組みを紹介いただきました。大塚氏は、ご自身の介入研究をもとに、感謝することを通じ、抑うつやストレスが減少することや、周囲への働きかけ(対人的援助)により、同僚のサポートも高まるなど、周囲へも好影響を及ぼすことを明らかにしました。また、それを実践するために、「職場の一体感を高める」(それによる対人的援助の誘発)ことや、「感謝カードを渡すだけではなく、自分から進んで『善い』と思える行動をする」ことを通じ、感謝のポジティブ・スパイラルを回すことが、「売り手よし」「世間よし」「世間よし」の「三方よし」につながることを説明されました。
「レジリエンスを高めるためにできる方法とは?」(西大輔氏)
続いて、生活のマネジメントの視点として、西大輔氏(国立精神・神経医療センター)より、「レジリエンス~しなやかに逆境を跳ね返すためには~」と題してお話しいただきました。西氏は、」レジリエンスを「逆境を跳ね返す、またはうまく対処する能力」と定義し、日常生活の中でそれを高めるための方法論を紹介されました。たとえば「社会的サポート」は、与え/与えられることが大事であること、身体運動がうつに対して有効であること、実践するためのモチベーションの高め方として、目標設定を低めにすること、体育の授業の悪い思い出は忘れること、とにかく楽しむことなど、ユニークな視点での問題提起をいただきました。また、自分の感情にも配慮し、「「What」ではなく、When」「Why」などを有効活用して自分への問いかけを行うことで、自身のポジティブな側面に光を当てていく方策があることを明らかにされました。
「自分の状態を知ることがエンゲイジメントへの第一歩」(種市康太郎氏)
次に、日々の仕事の中でいかにいきいき働くかについて、「『日記法』研究からわかった、日々、いきいき働くための3つのポイント」と題して、種市康太郎氏(桜美林大学特任准教授)よりお話しいただきました。種市氏は、「日記法」(同じ人物に同じ質問を繰り返し聞くことで、それぞれの時の状態を測る手法)により、その人の中の状態の違いを明らかにすることで、直接コンディションに影響する要因を知ることを目指しました。その結果、ワーク・エンゲイジメントは日内変動することが明らかになりました。それとともに、そこに影響を与える要因として、直接的には個人資源(自己効力感、自尊感情、楽観性、エネルギー、ポジティブ感情)と、間接的にはリカバリー(仕事からの解放による回復)、仕事資源(高い自律性、チーム力、上司行動)があるとのことでした。また、「仕事の要求度」は、「ブースター(増幅)効果」があり、資源が十分あればエンゲイジメントをさらに高め、逆であれば低める効果があることもわかりました。これらから、種市氏は①日々の自己効力感の向上(成功体験、過去の成功想起、モデリング)②次の仕事へのリカバリー(オンとオフ、休息、仕事以外の活動)、③仕事資源向上(自律性確保、チーム風土向上)が実践へのポイントとなると説明しました。
ゲストによる問題提起
「実践を裏付けるものとしての理論」(トヨタファイナンス・矢田真士氏)
続いて、ゲストからの問題提起として、まずはトヨタファイナンス株式会社人事部長の矢田真士氏より、「TFCの『企業文化変革活動』における理論を生かした職場改善事例のご紹介」と題して、同社において進められている組織文化変革活動と理論の関連性が語られました。
矢田氏は、同社が目指す組織文化~人を大切にする会社~の実現活動、具体的には働き方の変革、マネジメント・社員の変革~は、実はワーク・エンゲイジメントという言葉に収れんされるものだった具体的な改善事例を挙げて語りました。あわせて、理論と実践を関連付けるうえでは、①理論を形のみ入れるのではなく、「何を実現したいのか」がないと失敗する②それとともに本質に迫る具体的な深堀が欠かせないことも併せて説明しました。
「理論で得られた財産が支えになった」(東京大学大学院・武村雪絵氏)
お二人目のゲストとして、東京大学大学院看護管理学分野の准教授の武村雪絵氏に、「看護管理の現場から『理論を学ぶことの意義』」と題してお話しいただきました。武村氏は、以前大学教員から転じて大学附属病院で副看護部長・看護部長を務めた経験から「理論と実践」について語ってくれました。「にわか管理職」として赴任された武村氏にとって、大学院時代に学んだ経営学や組織論の知識は財産になっており、ひいてはそれが「ミッションとエンパワーによる管理」を推進するうえでのバックボーンになったとのことでした。かつて学んだ組織論のアプローチが、「語り合いつつ目標を作る」ことによるメンタルモデルの共有と、そのうえでのエンゲイジメントの起点になったとのことでした。
このあと、登壇者によるパネルディスカッションで、「理論と実践の融合を目指して」と題して、会場からの質問も受けつつ様々な討議が行われました。また、終了後、会員限定コミュニティが開催されました。本コミュニティでは、通常の会員間、登壇講師との交流に加え、「理論を産業現場での実践につなげるには」というテーマで、登壇者も交えたグループ討議が行われました。
(質疑内容やコミュニティの内容は会員限定で公開。メニューより会員ログイン後に質疑応答・コミュニティの様子と当日の資料をご覧いただくことが可能です)
次回開催は12月14日のシンポジウムです。シンポジウムでは、2016年の定例セミナーテーマについてもご案内します。ご期待ください。
続きは個人会員 / 協賛会員 / 組織会員 / AWP研究科同窓会組織のみ、閲覧可能です。
会員ログイン