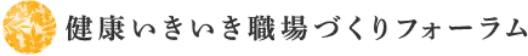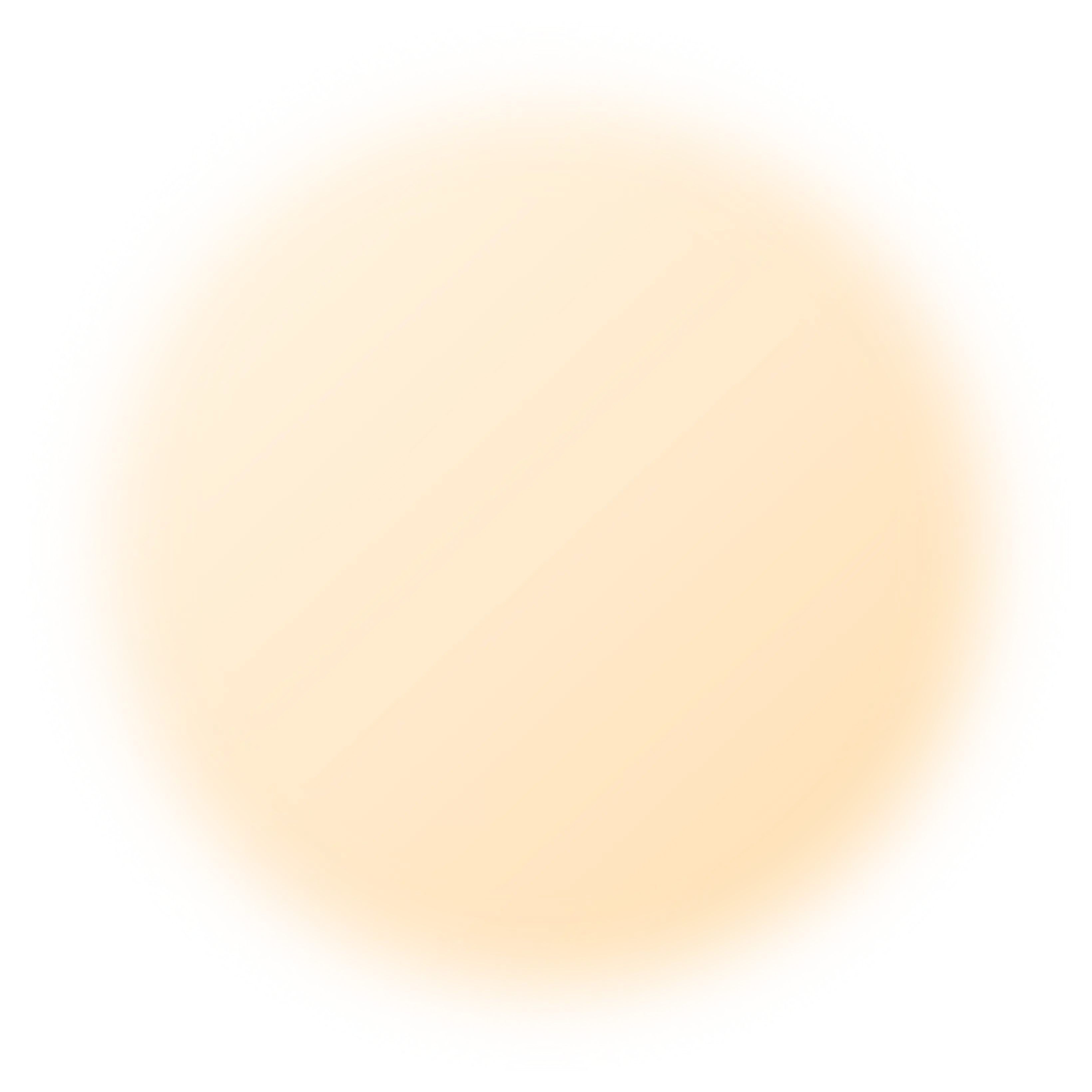6月3日(月)、Active Work Place研究会第1回がスタートいたしました。
本研究会は、健康いきいき職場づくりの理論や方策を学ぶ場でありながら、自組織の職場づくりをどのように推進していくのかを考える、実践の場でもあります。初年度、第1期生として、6社11名のメンバーが集まりました。ここから生まれる様々な実践知を、フォーラム活動の中でもできる限り紹介し、フォーラムに集まる方々が健康いきいき職場づくりに取り組むきっかけを得ていただければと思っております。メンバーの皆さん、1年間の学びと実践が充実したものとなるよう、共に頑張って行きましょう!
第1回は、川上教授より、「健康いきいき職場づくりとは」として総論講義をいただく中で、Active Work Place研究会が目指すものについてお話をいただきました。川上教授からは、参加組織が必ず良い方向に進めるよう、全面的に支援をいただけるとの心強いメッセージが伝えられました。
その後、参加メンバーより自組織の紹介と参加理由、課題認識について、お話をいただきました。今回のメンバーは、組織の規模も業種も様々であることから、多様なお話を伺うことができました。しかしいずれの企業も、環境変化に伴う組織の不活性状態に問題意識を持ち、これを打開するためのポジティブなアプローチを、この研究会で学び取ろうとされていました。
次に事例紹介として「株式会社サイバーエージェント」の人事部門のマネジャーの方にお越しいただき、同社の展開する「組織の一体感の最大化」をテーマに、多くの取り組み施策についてお話いただきました。同社の事例は、若いベンチャー企業ならではと言えるものも多くありますが、一方で、「マキスムズ」という行動指針の徹底的な浸透や、人事が施策を講じる際に必ず「白けのイメトレ」をする(ある人事施策を展開する場合、それが社員に受け入れられないパターンを何度も深く検討すること)ことなど、どの企業組織でも実践すべきことを根底でしっかりやっていることに気付かされます。また同社の取り組みは、心理学の理論の裏づけもできる内容と、島津准教授も指摘されていました。
講演の質疑応答も含めたランチタイムの後、午後はグループワーク中心のプログラム展開です。グループワーク①では、なぜ、企業が健康いきいき職場づくりに取り組むのか、その目的・目標を明確にするために、「組織目標」のための「健康いきいき職場づくり」であることのロジックを考えました。これをしっかり説明できると、この活動を、特に経営者やその他関係者に説明する際に説得力が増します。また、健康いきいき職場づくりの位置づけや重要性を明確にできるため、担当者自身も、手段の目的化を防ぐことができます。健康いきいき職場づくりに取り組もうとする企業、労組、また各職場の皆さんにはぜひ、最初に実施してほしいワークです。

グループワーク②では、自社の健康いきいき職場資源のリストアップツール作りを行いました。参加メンバー自身が考える、職場に今ある「資源」と、あったら良いと考える「資源」をリストアップします。結果的には17のテーマにグループ分けされた、100を超える「資源」が提案されました。今回のワークには時間制限がありましたが、おそらくまだまだ多くの「資源」が、それぞれの職場にあるのではないでしょうか。研究会後の「実践課題」では、メンバーが自組織に戻り、さらに強化したい「資源」は何か、また当日挙げられなかった新しい「資源」はないか、職場から探してきていただきます。

グループワーク③では、参加企業ごとに、Active Work Place研究会に参加しての目標について、川上教授、島津准教授も1社ずつアドバイスに入りながら、じっくりと話し合いが行われました。Active Work Place研究会は、参加された方々が、ただ学ぶだけでなく、毎回の「実践課題」に応じて、実際の職場へアプローチしながら進める必要があります。それだけに、どの部署で行えるか、どのように上司や社員の理解を得るのかなど、準備や調整に大きく時間をかける必要があります。これは、本研究会だからということではなく、実際に「職場づくり」に取り組もうとする際の最初のハードルとなるかもしれません。部門調整や効果的な推進方法については、第3回で議論したいと思います。
終了後の懇親会も大変盛り上がり、Active Work Place研究会での実践が、必ずやうまく行くことに期待を新たにいたしました。
第2回はもうすぐ、6月24日(月)の開催です。どうぞお楽しみに!